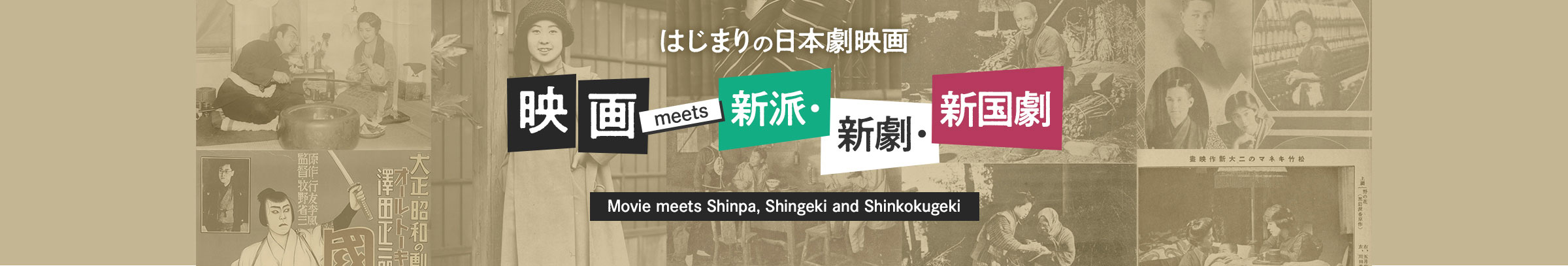このサイトについて
本サイトは、「はじまりの日本劇映画 映画 meets 歌舞伎」に続き、国立映画アーカイブが所蔵する日本の劇映画作品をデジタル化して配信公開する2つ目のサイトです。
映画と新派・新劇・新国劇との関係を考えれば、本格的なトーキー時代を迎えて「台詞を言える俳優」が求められるようになった1930年代後半以降から映画で活躍を始めた、舞台出身の数多の名優たちの姿が思い浮ぶでしょう。しかし本サイトで扱うのは、俳優の声を必要としない無声時代の映画作品です。
明治時代の欧化政策の中で、日本の伝統的な演劇である歌舞伎の「改良」が求められる一方で、新しい演劇ともいえる舞台が生まれました。その始まりのひとつに自由民権運動と深いつながりを持つ壮士芝居・書生芝居=新演劇があり、新演劇に洋行の見聞と戦争を題材として取り入れて興行的成功を収めたのが川上音二郎でした。音二郎は巡業も含めて生涯に4度も海外に赴き、欧米の劇界での経験と見聞をもとに日本の演劇界の改革を目指し、近代演劇のパイオニアのひとりとなりました。音二郎の影響を受けつつ、新演劇の持つ政治性から距離を置いた伊井蓉峰たちの流れは、近代演劇としての写実性を保ちながら歌舞伎との親和性も高い新派として実を結び、他方では音二郎による海外戯曲の翻案上演に対する坪内逍遥や小山内薫たち専門家側からの応答として、忠実な翻訳劇上演への取り組みが始まり、それは20世紀の日本演劇史の大きな潮流となる新劇へと展開してゆきました。そして、逍遥に学んだ近代的舞台俳優として出発した澤田正二郎が恩師の励ましを受けて、新派でも新劇でも歌舞伎でもない、新しい国劇の創造を目指して大正時代に旗揚げした劇団が新国劇でした。
日本の近代演劇は明治時代にすでに映画と交錯していました。1897年1月に稲畑勝太郎が持ち帰ったリュミエール兄弟の映像装置シネマトグラフが同年3月に東京で初公開されたのは、川上音二郎が神田三崎町に自費で建設した川上座においてでした。シネマトグラフの興行の前にこの劇場で上演されたのは、音二郎一座がジュール・ヴェルヌの小説を翻案・劇化した『八十日間世界一周』でした。川上座の観客は前の月に舞台装置として見た外国の風景が、次の月には新たな発明品である「動く写真」によって実際の風景として映し出されるのを目の当たりにしたのです。また、1908年に吉澤商店が目黒に日本初の撮影所を開設すると、その最初期に川上音二郎一座の喜劇が撮影されました。
本サイトで公開するのはいずれも1920年代前半に製作された作品です。撮影所での映画製作が始まった1908年からでも10年余りが経過しており、サイト名に「はじまり」を冠することは疑問を抱かせるかもしれません。それでは、その10数年間に日本映画は何を経験したのでしょうか。
本サイト「深く知る」に寄稿いただいた大笹吉雄氏の論考は、日本の近代演劇の誕生を「女優誕生」、「新しく生まれた演劇や劇場」、そして変革の担い手としての「素人」という3つのポイントで説明しています。興味深いことにその3つは、1910年代後半から20年代初めの日本の映画界の状況にもあてはめることができます。
映画は1910年代に庶民の娯楽として広く支持を集めるようになるにつれ、説明役である弁士の存在が大きくなってゆきました。特に日本映画の場合には、複数の弁士が声色を使って陰台詞をつける上映方法が定着し、人気弁士たちの声を活かせる映画作りが興行側から求められたことで、彼らが語りやすいように、舞台そのままを長回しで撮影したような画面の作品が作られていました。そこでは女性役は女形が演じることが一般的でしたが、歌舞伎の様式性を引き継いだ旧劇映画はともかく、新派劇とも呼ばれた現代劇では、映像で見る女形の不自然さが指摘されるようになりました。興行側が主導権を持っている状況を変えようとする様々な試みの中で最も先進的だったのが、映画理論家で製作については素人だった帰山教正らの「純映画劇運動」でした。帰山は女優を起用し、外国映画に学んだ映画話法をベースにスポークン・タイトル(台詞字幕)を含む中間字幕を適切に使い、弁士の存在に頼らずに物語を伝えることのできる「映画劇」の製作を提唱して自ら実践しました。女優の起用と映画劇の製作を最初から打ち出した松竹キネマの創立は1920年でした。つまり1910年代末から20年代初めは、新しい話法を持った日本の劇映画がはじまり、演劇の世界から多くの人材を得て、日本映画がその形を大きく変えようとした時期でした。
1923年の関東大震災後の復興の中、映画館数も観客数も増えて映画産業が拡大したことが変革を押し進めました。映画産業の隆盛を誇るかのように、映画館は震災復興期のバラック建築から、レビューなどの上演も可能な堂々たる劇場建築へと建て直されてゆき、1920年代後半から30年代前半にかけて、日本映画は無声映画の輝かしい完成期を経てトーキー時代に移行してゆきました。
本サイトが、日本の映画と演劇の豊かな交流の歴史にあらためて思いを馳せるきっかけとなることを願います。
国立映画アーカイブ