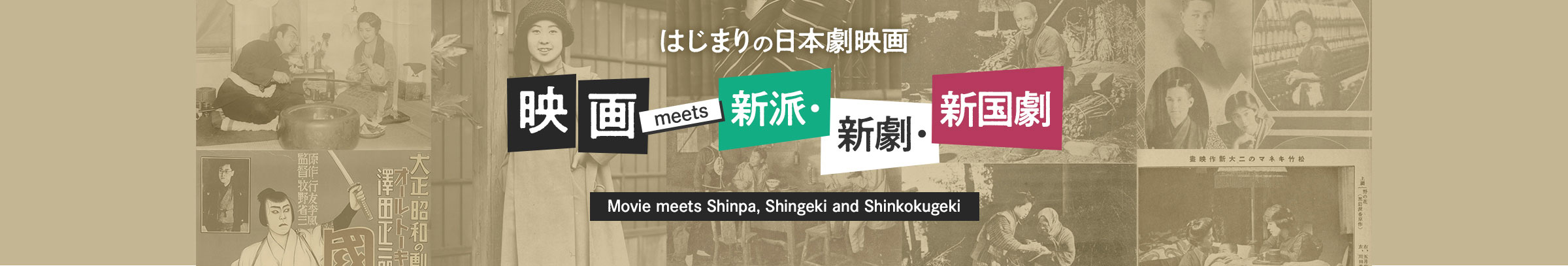寒椿
水車小屋番の老父と娘の悲劇を描いた新派劇の映画化作品で、1920年代前半の短い活動期間で終わった国際活映(国活)の数少ない現存作品の1本。主演は、現状に安住することのない開拓者的な活動で「新派の異端児」と呼ばれた井上正夫で、名前を伏せて映画初出演を果たした水谷八重子(初代)は、こののち演劇活動を本格化させて、新派と新劇を中心に1970年代終わりまで長く第一線で活躍した。舞台での共演も重ねた2名優の出会いの作品として演劇史的な意味も認められよう。
映画詳細
- 映画題名
- 寒椿
- 映画題名ヨミ
- カンツバキ
- 製作年(西暦/和暦)
- 1921(大正10)年
- 解説
-
大正時代から舞台と映画を横断的に行き来し、現状に安住することのない開拓者的な活動で「新派の異端児」と呼ばれた井上正夫の主演作で、新派、新劇を中心に大正、昭和と第一線で活躍し続けた水谷八重子(初代)の映画初出演作でもある。のちに多くの舞台で共演した名優たちの出会いの作品として演劇史的な意味も認められよう。
1910年代半ばに舞台と映画を組み合わせた連鎖劇に取り組んだ井上正夫は、新派の舞台に戻ったのち、創立間もない国際活映株式会社(国活)に厚遇で招かれて半年間にわたるアメリカ映画界視察を行った。国活は天然色活動株式会社(天活)の創立者のひとりで、独立して小林商会を起こした小林喜三郎が『国民の創生』(D・W・グリフィス監督、1915年)の興行で成功をおさめて1919年に設立した会社で、設立後まもなく巣鴨に撮影所を持つ天活を買収し、さらに角筈にも撮影所を開設した。井上に国活入りの話をもたらし、アメリカ視察を共にしたのは、その角筈撮影所長で本作では脚色を担当した桝本清だが、彼は小山内薫と市川左團次の自由劇場に刺激を受けた井上が、1911年に新時代劇協会を起こした際の協力者でもあった(参考文献⑬145、198頁)。
映画初出演の水谷八重子は雙葉高等女学校在学中であることを憚って「覆面令嬢」としてクレジットされたが、当時の映画雑誌の記事では水谷の名前は明かされており、監督の畑中蓼坡ともすでに舞台の仕事を共にしたことがあった。舞台と映画を横断的に活動するという点では水谷も井上に劣らなかった。水谷は新劇と新派の枠を超えて活躍した一方で、映画にもしばしば出演した。参考文献(⑭59-60頁)によれば、1926年に渡米してハリウッドを見学した際に感銘を受けたことが映画出演を続けた理由としている。
1910年代後半は日本の劇映画の変革の時期だった。日本活動写真株式会社(日活)の向島撮影所では田中栄三らにより、女形を使いながらも、場面転換を増やしたり、照明を使った撮影を試みたりした「革新映画」と呼ばれる作品が製作され、桝本清も脚色者として参加していた。帰山教正らの「純映画劇運動」はより急進的な映画革新の提唱だった。その実践として、帰山は自身が輸入係を務めていた天活の重役を説得して『生の輝き』と『深山の乙女』の製作を実現し、両作品とも1919年に公開された。天活が国活に買収されると帰山らの活動も引き継がれたが、弁士の役割の排除に向かうと考えられた映画劇の製作には興行側からの反発が強く、国活は映画芸術協会との関係を解消した。これにより急進的な革新運動は抑えられたかに見えたが、日本の劇映画が「映画劇」的表現に向かう流れが止むことはなかった。
その国活で製作された本作は、アメリカ帰りの新進気鋭の演劇人である畑中蓼坡が監督し、アメリカ視察を終えた井上正夫が出演する映画劇としての期待がある一方、弁士が力を持つ興行側からの要望も容れざるを得ない会社側の思惑もあり、撮影を担当した酒井宏(当時、酒井健三)の回想(参考文献⑮)によれば、「サブタイトルだけにして、スポークン・タイトルは一切省略するが、カット・バック、大写しの手法は差支えない限り適宜に挿入することは妨げない」という方針が採られたという。元素材でも会話場面には短い言葉以外はほとんど字幕が出てこないことが確認され、説明がなければ物語の要所を充分に理解できない可能性が高い。また井上自身が「「寒椿」は通俗的なもので、映畫劇に對する私の眞の目的にそぐわない爲め、可なり不滿を抱きながらも、營利上これを演技し且つ公開するの止むを得なかつたのです。」(参考文献⑩)と表明しており、小島孤舟の原作『湖畔の家』が新派の戯曲であったことへの先入観も併せ、新しい映画劇を期待する人々からは批判を受ける余地を残したといえる。なお、本作と同じ月には松竹キネマ研究所第1回作品『路上の霊魂』(村田実監督)が公開された。
数寄屋橋近くにあった日本初の西洋式劇場の有楽座における初公開は、井上正夫が出演する『酒中日記』(国木田独歩原作、真山青果脚色)の上演が組み合わされており(参考文献①、②)、当時の観客にとっては井上を映画と実演で見る機会となった。『酒中日記』には畑中も俳優として舞台に立った。なお、この公演を伝える記事(参考文献③)から、上映の説明を担当した弁士は松浦翠波だったと考えられる(記事中では「松」ではなく「杉」になっている)。
参考文献(⑧)によれば、撮影は山梨県の上野原近郊の水車小屋、多摩川の上流、別荘は目黒でロケが行われ、別荘の中は角筈撮影所にセットが組まれたが、水谷の病気で撮影が一時中断したという。また、参考文献(⑮)によれば、「ラストシーンの月はパテーカメラによる合成である」という。
朝彦を演じた高勢實(高勢實乗)は俳優としては新派の流れをくむ。衣笠貞之助監督『狂った一頁』(新感覚派映画連盟=ナショナルアートフィルム社、1926年)『十字路』(衣笠映画聯盟=松竹キネマ、1928年)で強烈な存在感を見せたが、トーキー時代に入って喜劇俳優に転じて活躍した。朝彦の許嫁貴美子を演じた林千歳については『救の手』の解説で触れる。また、おすみをいじめる別荘の女中のひとり、お咲を演じた宮部静子は坪内逍遥の文芸協会演劇研究所の第3期生だったが研究所が閉鎖され、舞台協会を経て島村抱月と松井須磨子の芸術座に参加した経歴を持つ。
国活は1921年後半から急速に経営が傾き、同年夏には角筈撮影所は閉鎖される。撮影所長だった桝本清は小プロダクションで映画に携わったのち、桝本実用映画制作社を設立して教育映画製作に乗り出した。
※説明および台詞字幕の少なさを補うため、以下に粗筋を添える。
村はずれの水車小屋に娘おすみと暮らす吾助は、借金のある林造から金の返済か、おすみを嫁に出すかを迫られている。おすみは伯爵嗣子の朝彦とその許嫁の貴美子と偶然知り合ったことで、伯爵の別荘の小間使いになる。別荘の桃の節句の小宴の折、朝彦がほろ酔い加減の冗談におすみを妻に迎えると言って指輪を与える。それを信じ込んだおすみは吾助に報告に行く。その後、泥酔した林造から責められた悟助は指輪を見せて、おすみと朝彦との婚約話を明かしてしまう。逆上して鎌を手に別荘に向かおうとする林造を必死で押しとどめる悟助は、誤って彼を殺してしまう。死を決意した吾助は別荘に朝彦とおすみを訪ね、それとなく別れを告げて出て行く。入れ違いに来た刑事から吾助の容疑が別荘に伝えられ、手土産に添えられた吾助の手紙を読んだ朝彦は、自分の軽率な行為が純朴な父娘を不幸にしたことを知る。水車小屋で首を吊ろうとする吾助を、刑事は説得の末に思いとどまらせる。山道を行くふたりにおすみが追い付き、結婚話の真実を知った悟助は力を落としてしまう。後から駆け付けた朝彦がおすみの将来を約束すると、悟助は気を取り戻して刑事に連行されてゆく。 - 時間(分)
- 86
- サウンド
- サイレント
- カラーの種類
- 染色/白黒
- 製作会社
- 國際活映株式会社(角筈撮影所)
- 公開年月日
- 1921年4月24日(有楽座)
- スタッフ
- 畑中蓼坡[監督]小島孤舟[原作]桝本清[脚色]酒井健三[撮影]齋藤五百枝[舞台意匠]賀來淸三郎[字幕意匠]
- キャスト
- 井上正夫(水車小屋の主人戸畑伍助)覆面令嬢[水谷八重子](悟助の一人娘 おすみ)吉田豊作(乘合馬車の禦者川北林造)高瀬實(伯爵の嗣子 花岡朝彦)林千歳(朝彦の許嫁 貴美子)水島亮太郎(伯爵家の家令 石塚源之進)宮部靜子(伯爵家の侍女 お咲)御園艶子(仝 お梅)星素[志賀靖郎](刑事 山田一作)
- 検閲番号等
- 元素材には検閲番号の穿孔跡があり、以下の検閲時報の記録と合致する。
1939年11月22日
8175、日 現 人 悲、無、寒椿、7巻、1614m、國際活映社(製作者)、セカイフイルム社(申請者)
元素材はメートル換算で1570.674m。 - 映写速度
- 16
- 備考
- 元素材は、2012年度に日本大学藝術学部より受贈した染色版35mm可燃性上映用ポジフィルム(フィルムストック:GEVAERT BELGIUM、尺長:5153フィート13コマ)。
- 参考文献
- ①有楽座広告(『讀賣新聞』1921年4月23日付)1面
②「寒椿/酒中日記」筋書[有樂座、1921年](早稲田大学演劇博物館デジタルアーカイブ/演劇上演記録データベース)https://enpaku.w.waseda.jp/db/ [上演IDNo.]08541-30-1921-04-03
③山の手閑人「國活の井上へ(上)」(『東京朝日新聞』1923年4月30日付夕刊)3面
④山の手閑人「國活の井上へ(下)」(『東京朝日新聞』1923年5月1日付夕刊)3面
⑤芳湖生「映畫で見た寒椿」(『讀賣新聞』1921年5月7日付)6面
⑥「ふたば 寒椿(五巻)」(『キネマ旬報』第六十五號、1921年5月11日)8-9頁
⑦川村花菱「映畫劇の技巧と芝居の技巧 「寒椿」を見る」(『演藝畫報』第八年第六号、1921年6月)30-31頁
⑧津山いま子「新劇壇の新星 水谷八重子さん」(『演藝畫報』第八年第六号、1921年6月)94-98頁
⑨長尾百生「映畫に現はれた井上正夫 『寒椿』を見て」(『新演藝』第六卷第六號、1921年6月)96-99頁
⑩井上正夫「「寒椿」に就て」(『新演藝』第六卷第六號、1921年6月)98-99頁
⑪「山家に育つた可憐な娘の人情哀話 寒椿」(『活動之世界』第一卷七月號、1921年7月)46-49頁
⑫綠川春之助「映畫雜感 國活會社の新映畫「寒椿」」(『活動之世界』第一卷七月號、1921年7月)62-64頁
⑬井上正夫『化け損ねた狸』(右文社、1947年)141-148、195-205頁
⑭水谷八重子『女優一代』(読売新聞社、1966年)19-21、28-30、59-60頁
⑮酒井宏「映画技術史資料 私の周辺に展開した映画技術史(2)」(『映画テレビ技術』№214、1970年6月)51-54頁
⑯吉田智恵男、市橋才次郎「高勢實乗」(『日本映画俳優全集 男優編』(キネマ旬報社、1979年)316-318頁
⑰盛内政志、市橋才次郎「宮部静子」(『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報社、1980年)677-678頁 - 関連リンク
-
- 「日本劇大會 (活動館(所在地不明) 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=249994 - 「特別超大興行 (桐生能楽館 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=250671 - NFAJデジタル展示室 第22回 無声期日本映画のスチル写真(10)─マキノプロダクション② 『湖畔の家』(1930年)(NFAJデジタル展示室)
https://www2.nfaj.go.jp/onlineservice/digital-gallery/nfaj-digital-gallery-no-22/
- 「日本劇大會 (活動館(所在地不明) 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)