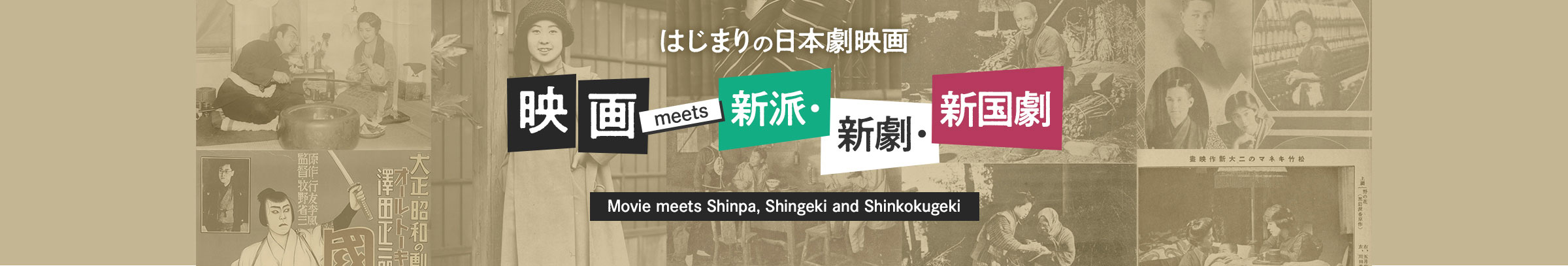救の手
労働者の生活を支える簡易保険の有用性を説いた周知宣伝映画で、坪内逍遥の文芸協会演劇研究所で松井須磨子と同期で学び、日本演劇史の女優の草分けのひとりとなった林千歳が出演している。簡易保険事業の周知宣伝を前提とした作りながら、一般公募した筋書をもとに小山内薫が携わったという脚色には、自動車と列車の追跡場面をクライマックスに取り入れるなど、観客の関心を惹きつけるための映画的な工夫も凝らされている。
映画詳細
- 映画題名
- 救の手
- 映画題名ヨミ
- スクイノテ
- 製作年(西暦/和暦)
- 1921(大正10)年
- 解説
-
簡易保険事業の周知宣伝のために製作された映画で、小山内薫が脚色を担当し、日本の女優の草分けのひとりである林千歳が主演している。林千歳は日本女子大学校文学部入学後、坪内逍遥の文芸協会演劇研究所に入って演劇活動をはじめる一方、平塚らいてうの『青鞜』にも参加する先進的な女性だった。補欠募集で入所した演劇研究所では松井須磨子と同じ第1期生だったが、卒業は澤田正二郎と同じ第2期生としてだった。参考文献(⑬100頁)によれば、同期の林和との交際が会規に抵触して演劇研究所を退所したが、林とは結婚して、のちに復帰が許された経緯があったという。在所中に初舞台を踏み、卒業後に文芸協会が解散すると夫とともに舞台活動を続けるが、1919年に公演直前の役を降りてそのまま演劇界を去り、翌年国活角筈撮影所に招かれて映画界に転身した。井上正夫の国活第1作『寒椿』で助演、次の『海の人』(細山喜代松監督、1921年)では井上の相手役を務めたが、国活の経営が傾いて角筈撮影所が閉鎖すると巣鴨撮影所に移った。本作はその時期の出演作品である。その後、松竹蒲田に招かれて多くの映画に出演するが、戦時中に映画界からも引退した。
参考文献(⑩)によれば、簡易保険の周知宣伝映画は1917年の『隣同士』が第1作で、常設映画館ではなく、保険思想の普及や簡易保険の勧誘を目的とした講演会場などで上映されたという。周知宣伝効果が認められて製作が続けられ、1929年以降は常設映画館でも公開されるようになり、『岐路に立ちて』(松竹蒲田、清水宏監督、1930年)などが知られる。
1919年には第2作のために初めて筋書の募集が行われ、逓信次官を審査委員長に、関係局長と小山内薫を審査員として選考が行われ、第1等当選の筋書が『漁夫吉之助』の題名で映画化された。なお3等当選に近藤伊与吉『鍛冶屋の杉さん』と島津保次郎『旭の昇る時』があり(参考文献①、②、③)、島津はこの入選が小山内と面識を得るきっかけになったという(参考文献⑪)。
簡易保険局の当事者によって本作の製作過程が明かされている。参考文献(⑥)によれば、1920年の第2回筋書募集の応募作860本から当局が100本に絞り、専門家として小山内薫に委嘱して入選を定め、内部の審査員8名により竹内純一『救の手』が第1等に選ばれた。第2等当選に友成用三『何を殘した?』がある。参考文献(⑦)によれば、脚色は小山内薫に委嘱され、簡易保険局の意見を取り入れつつ種々の変更が加えられた。筋書の梗概(参考文献⑥)と比較すると、映画では全体の時間経過が圧縮されており、自動車が列車を追跡するクライマックスも脚色で加えられた。簡易保険局は俳優の選考に重点を置き、『隣同士』に出演した井上正夫と帝劇女優の出演を望むが、脚本を読んだ井上は主人公と自身の年齢差を理由に断る一方、当時所属していた国活に口添えして、林千歳を含む所属俳優が出演することになった。出演者のうち葛木香一と大山武はすでに簡易保険映画第2作『漁夫吉之助』に主演していたという。脚色の小山内薫以外のスタッフは資料からは確認できていない。撮影は1921年10月17日から開始し、月末までに完成したという。撮影は栃木県塩原で山間の小学校を、埼玉県秩父附近でクライマックスの追跡場面を、紡績工場、病院や社長宅など「悉く實寫に依る」と、ロケーション撮影中心に進められたとあるが、下宿の部屋や工場の事務室などは国活巣鴨撮影所のセットと考えられる。中間字幕による場所や状況の説明に加え、手紙の文面のカットや回想シーンの挿入、列車追跡場面のクロスカッティングなどの手法が使われているが、スポークン・タイトルは少ない。例えば主人公夫婦の食事場面は長さの割に会話の内容は不明だが、参考文献(⑦)に「映寫上の希望」として説明の注意点が挙げられており、この場面の長さについては「主人公夫妻をして簡易保險に加入せんとする動機を説明者に語らしむる爲め」であるとし、通常の映画興行における活動弁士への配慮というよりは、簡易保険の周知及び勧誘の説明を入れるための「間」であったことが分かる。また、「調製上の工夫」についても詳説しており、中でも列車追跡場面について「舶來映畫の手法を用ひた」と表明している点は興味深い。
※説明および台詞字幕の少なさを補うため、以下に粗筋を添える。
裕福な実家を出て山間の小学校の教員となった清水國雄は、下宿の娘君子との結婚を認めない父の手紙に失望して遊蕩に走り、借財を抱えて出奔。都会の紡績工場でボイラー火夫の職を得る。ある日、國雄は職工長の木村と揉めた工員から彼らの不正を聞くが、木村からは逆に脅しを受ける。國雄の生活は君子の来訪が転機となる。結婚を認める父の手紙がもたらされ、ふたりは社長の媒介で結婚。君子も工場で働くようになる。ある時、将来への不安を口にする國雄に君子は簡易保険を提案して一緒に加入する。証書を手にした國雄は生活の保障を得て心を強くする。会社の花見で國雄は木村を諭すが争いになり、来合せた社長に國雄はやむなく事情を説明する。数日後、國雄が木村に代わって職工長になる。逆恨みした木村の細工でボイラーが爆発し國雄は負傷する。汽車で逃げた木村を自動車で追った工員たちが捕える。國雄は駆けつけた父たちに簡易保険は救の手だったと話す。捕まった木村は深く謝罪する。後日、全快した國雄は君子と父を連れて社長を訪ねたあと故郷へと向かう。 - 時間(分)
- 39
- サウンド
- サイレント
- カラーの種類
- 白黒
- 製作会社
- 簡易保險局[調整]、國際活映株式會社(巣鴨撮影所)
- 公開年月日
- 1921年10月(完成)
- スタッフ
- 竹内純一[原案]小山内薫[脚色]
- キャスト
- 葛木香一(淸水國雄)林千歳(堀君子)木村正夫(職工長 木村爲三)大山武(社長 杉田保)
- 映写速度
- 18
- 備考
- 元素材は、2000年度にロシア・ゴスフィルモフォンドより入手した35㎜不燃性ポジフィルム(フィルムストック:ORWO 829、尺長:2342フィート4コマ)。
- 参考文献
- ①「活動寫眞劇筋書募集」(『官報』第二〇八五號、1919年7月17日)404頁(国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/pid/2954198/1/8
②「懸賞簡易生命保險活動寫眞劇筋書當選」(『官報』第二一六八號、1919年10月25日)634頁(国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/pid/2954281/1/7
③「簡保奬勵活動脚本」(『保險銀行時報』第九百四十九號、1919年11月)8頁
④「筋書募集」(『官報』第二四九三號、1920年11月22日)527頁(国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/pid/2954608/1/9
⑤「懸賞簡易生命保險周知用活動寫眞筋書當選」(『官報』第二五九五號、1921年3月30日)764頁(国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/pid/2954710/1/11
⑥監理穩士「懸賞募集保險劇筋書發表に就て」(『遞信協會雜誌』第百五拾六號、1921年6月)75-77頁
⑦猪熊貞治「新作保險劇『救の手』に就て」(『遞信協會雜誌』第百六拾參號、1922年1月)59-63頁
⑧川船摸「保險思想宣傳用の映畫に就て」(『保險銀行時報』第一千六十五號、1922年2月)5頁
⑨岡崎樂天「工女に對する保險勸誘」(『遞信協會雜誌』第百六拾九號、1922年7月)35-36頁
⑩『簡易生命保險郵便年金事業史』(簡易保險局、1936年)349-368頁
⑪田中純一郎『日本映画発達史Ⅰ 活動写真時代』(中公文庫、1975年)312-313頁
⑫田中純一郎、奥田久司「林千歳」(『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報社、1980年)530-531頁
⑬菅井かをる「日本女子大学校と演劇――女優林千歳の軌跡を手掛かりとして」(「新しい女」研究会[編]『『青鞜』と世界の「新しい女」たち』日本女子大学叢書6、翰林書房、2011年)96-111頁