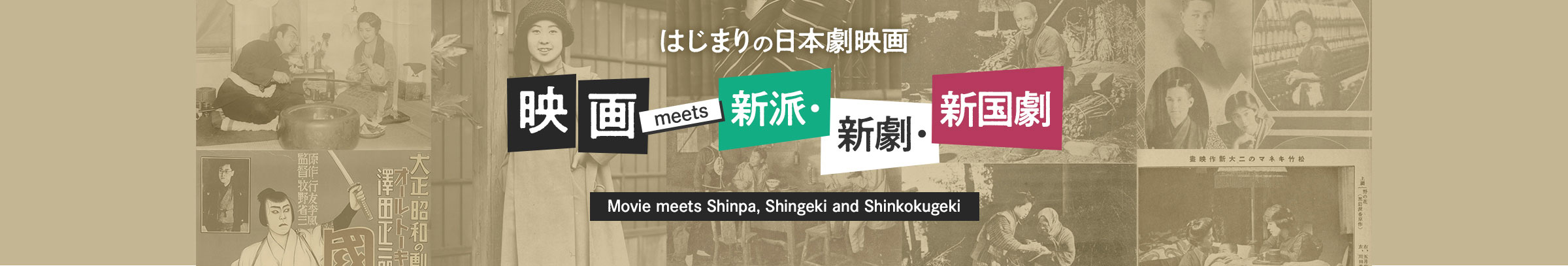收穫
都会生活で傷ついた女性が故郷の農村で新しい生活をはじめる姿を描いた社会教育劇で、日本映画の革新を目指した「純映画劇運動」の実践作『生の輝き』(1919年)に主演して、「日本の映画女優第1号」とされる花柳はるみの現存が確認されている唯一の出演作品である。製作会社の活動写真資料研究会は、社会運動家から映画事業に乗り出した高松豊次郎が設立した会社で、「婦人問題劇」を謳った本作のような啓蒙的な社会教育映画の製作と常設映画館での興行を試みた。
映画詳細
- 映画題名
- 收穫
- 映画題名ヨミ
- シュウカク
- 製作年(西暦/和暦)
- 1921(大正10)年
- 解説
- 1919年公開の純映画劇運動の実践作『生の輝き』と『深山の乙女』(いずれも天活、帰山教正監督)への出演によって、「日本の映画女優第1号」とされる花柳はるみの数少ない映画出演作で、現存が確認されている唯一の作品である。
花柳はるみは帰山教正監督第3作『白菊物語』(1920年)に出演後、松竹キネマ最初の作品として製作された村田実監督の『奉仕の薔薇』に出演するも公開が遅れてしまい、同社の女優第1号を『島の女』(ヘンリー・小谷、木村錦花共同監督、1920年)に出演した川田芳子に譲ることとなった。本作への出演後、花柳は舞台活動に専念し、小山内薫から招かれて築地小劇場に参加すると、同劇団最初の『桜の園』ではラネーフスカヤ夫人を演じ、畑中蓼坡の新劇協会では看板女優の伊澤蘭奢と姸を競うなど、大正後期から昭和初期の新劇の舞台で活躍するが、1929年に舞台を退き、結婚して完全に演劇界から身を引いた。参考文献(⑨、⑩)によれば、引退の年に新宿武蔵野館の実演に出演しており、4月には「バアレスク」『メトロポリス』で「マリア(女傳導師)」を演じ(関連サイト「MUSASHINO WEEKLY 9巻15号」参照)、7月には新劇協会公演となった関口次郎作、畑中蓼坡演出・出演の「ヴォードビル」『女優宣傳業』の「女優D」を演じた(関連サイト「MUSASHINO WEEKLY 9巻30号」参照)。引き続いて同協会公演となった次の週の『勇ましき主婦』が最後の舞台になったという(参考文献⑨)。演劇評論家の尾崎宏次は、花柳はるみを伊澤蘭奢とともに「歴史からこぼしてしまうことのできない女優」とする一方、「社会的にみると、彼女が初めて映画にでたときからあと、ヒューマニズムの洗礼をうけ、ダダイズムの水をあび、社会主義の風を受けて、ちょうど三つの時代思潮のなかでじぶんの「女優の歴史」をつくって、閉じてしまったといえる。」と記す(参考文献⑤)。1915年に芸術座で初舞台を踏んだ花柳の14年ほどの俳優人生の中で、映画出演はその前期に集中しており、おかっぱの断髪でナッパ服と呼ばれる作業着を着た写真の先端的なイメージは、その後の演劇活動を通して形成されたことになる。
本作を製作した活動写真資料研究会は、労働運動家であり社会活動を通じて映画事業に関わるようになった高松豊次郎が、社会教育映画製作のために結成した組織だった。参考文献(②)では題名に「婦人問題劇」の見出しが添えられ、作品の目的として「婦人の覺醒」「虚榮心の抑制」「禁酒」が示されている。元素材の残存部分では、「婦人の覺醒」にかかわると考えられる、花柳演じる主人公お光のエピソードが描かれた前半が欠落しており、井上麗三演じる要三が更生してゆく中盤部分のみが確認できる。欠落した前半では、幼馴染に誘われて農村生活と老父を捨てたお光の身の上が描かれた。お光はカフェーの女給となるが、都会生活に溺れた挙句に酒飲みの男と結婚して子供が生まれ、夫は喧嘩の怪我が元で死んでしまう。失意の中で美しい故郷を思い浮かべたお光は、帰郷して心優しい老父に迎えられて新しい生活を始める。同様に欠落している最後の方では、お光に横恋慕する小島が、彼女の家の納屋に放火して要三を陥れようとするものの、子供の証言などから嫌疑が晴れる展開だったという。
本作が公開された浅草の大東京は、高松豊次郎が活動写真資料研究会の活動の拠点とするために既存のMパテー館を改築開館した常設館で、本作は開館第2弾興行として山崎長之助一派の連鎖劇と併せて公開された。なお、のちに大東京は本サイトの配信作品『國定忠次』の東京封切館となった。高松の娘婿でもあった監督の山根幹人は、映画雑誌『活動之世界』の記者を経て活動写真資料研究会に参加。のちに東亜キネマに移り、等持院撮影所代理として牧野省三をささえた。東京で高松プロダクションを興した高松と牧野の仲介者の役割も果たしたと考えられる。また、のちに山根は東京シネマ商会で教育劇映画を監督し、戦時中は文化映画製作に携わった。
要三を演じた井上麗三(井上麗吉)は新派の佐藤歳三の門弟として俳優となり、松竹蒲田で栗島すみ子の初出演作『虞美人草』と第2作『電工と其妻』(いずれも1921年)に出演し、監督のヘンリー・小谷から多くを学んだという(参考文献③)。活動写真資料研究会では原作や脚本も手掛け、1924年に振進キネマを創立、以後多くの社会教育映画を世に送り出した。国立映画アーカイブの配信サイト「フィルムは記録する―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―」では、文部省製作で井上が監督した啓蒙宣伝映画『覺めよ國民』(1929年)を公開している(関連リンク参照)。 - 時間(分)
- 19
- サウンド
- サイレント
- カラーの種類
- 白黒
- 製作会社
- 活動寫眞資料研究會
- 公開年月日
- 1921年11月21日(大東京)
- スタッフ
- 山根幹人[監督・脚本]高松豊次郎[提供]
- キャスト
- 花柳はるみ(村山お光)井上麗三(淸水要三)中井正橘(小島藤吉)中川信水(倉田一郎)池田園子(女給お花)
- 映写速度
- 16
- 備考
- 元素材は、2021年度に曹洞宗寶珠山神龍寺より受贈した35㎜可燃性上映用ポジフィルムを不燃化した35㎜インターネガより作製した35㎜上映用ポジフィルム(フィルムストック:EK 2302-2021、尺長:1127フィート3コマ)。
この35mmプリントは2022年度の上映企画「発掘された映画たち2022」において上映されている。
収蔵時4巻のフィルムのうち復元できたのは2巻目と3巻目で、『活動倶樂部』1921年12月号によれば公開時は5巻とされている。 - 参考文献
- ①無署名「特殊敎育活動館 全國に六十箇所 淺草の元パテー館を改修し 第一歩の「大東京」 活動硏究會の新計畫」(『東京朝日新聞』1921年8月24日付)5面
②無署名「近く封切られる映畫劇收穫に就て 婦人問題劇 收穫(全五卷) 活動寫眞資料研究會作製」(『活動倶樂部』第四卷十二月號、1921年12月)75頁
③井上麗三「敎育映畫と私」(『活動俱樂部』第五巻二月号、1922年2月)76頁。岡部龍[編]『高松豊次郎と小笠原明峰の業績』(日本映画史素稿9、フィルム・ライブラリー協議会、1974年)に翻刻あり。
④靑地忠三「井上麗吉氏を憶う」(『視聴覚教育』第8巻第5号、1954年3月)20-21頁
⑤尾崎宏次『女優の系図』(朝日新聞社、1964年)201-228頁
⑥岡部龍[編]『資料 高松豊次郎と小笠原明峰の業績』(日本映画史素稿9、フィルム・ライブラリー協議会、1974年)
⑦田中純一郎「井上麗吉」(『日本映画監督全集』キネマ旬報社、1976年)52-53頁
⑧田中純一郎「山根幹人」(『日本映画監督全集』キネマ旬報社、1976年)429-430頁
⑨司馬叡三「花柳はるみ」(『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報社、1980年)525-527頁
⑩戸板康二『物語近代日本女優史』(中央公論社、1980年。文庫版は1983年)111-120頁[文庫版]
⑪上田学[編]『企画展図録「日活向島と新派の時代展」』(早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、2011年)47頁 - 関連リンク
-
- 『覺めよ國民』(1929年)(フィルムは記録する―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―)
https://filmisadocument.jp/films/view/178
※井上麗吉監督作品 - 「THE DAITOKYO 1号」(1921年)(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=227968
※「大東京」開館時のプログラム。 - 「MUSASHINO WEEKLY 9巻15号」(1929年)(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=231321 - 「MUSASHINO WEEKLY 9巻30号」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=231329
- 『覺めよ國民』(1929年)(フィルムは記録する―国立映画アーカイブ歴史映像ポータル―)