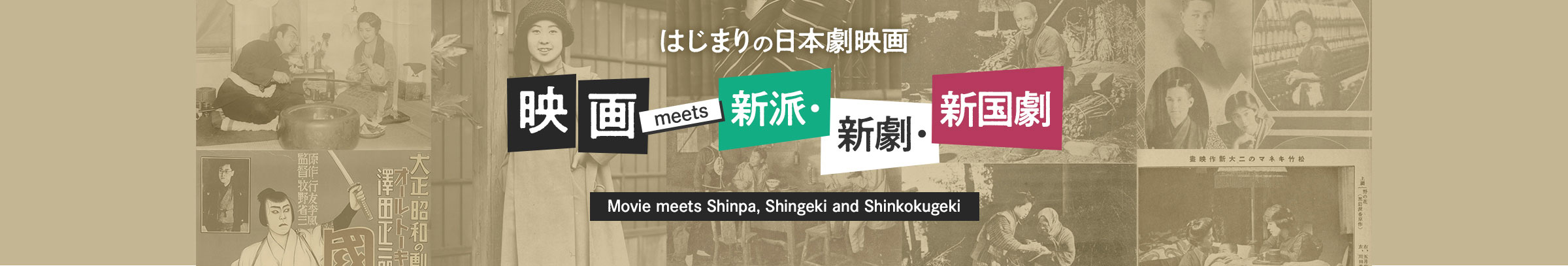ほとヽぎす
徳富蘆花の人気小説を舞台化して新派の「独参湯」といわれた人気演目の、松竹キネマでは初となる映画化作品で、初期の蒲田作品で多くのコンビを組んだ栗島すみ子と岩田祐吉が主演して大ヒットを記録した。現存しているのはいくつかの場面の断片にすぎないが、配役やロケーション撮影に「劇には見られない味が出てゐる」と評された、舞台劇とは異なる映画作品ならではの「味」の片鱗を伺うことはできるだろう。
映画詳細
- 映画題名
- ほとヽぎす
- 映画題名ヨミ
- ホトトギス
- 製作年(西暦/和暦)
- 1922(大正11)年
- 解説
- 不治の病とされた結核を理由に愛し合う夫、川島武男と離縁させられた浪子の悲劇を描いた徳富蘆花の小説『不如帰』の松竹キネマ最初の映画化で、多くのコンビを組んだ栗島すみ子と岩田祐吉の主演で大ヒットを記録した作品である。本作と前後して松竹では『金色夜叉』(賀古残夢監督)、『乳姉妹』(池田義臣監督)と、新派の演目の映画化が続いた。原作は1898年から翌年にかけて『國民新聞』に連載され、1900年に単行本が出版されるとベストセラーとなり、1901年に大阪朝日座の新派公演で秋月桂太郎の武男、喜多村緑郎の浪子の配役で劇化初演された。1908年に本郷座で初演された柳川春葉の脚色が以降の定型になり、新派の「独参湯」と呼ばれるほどの重要な演目として、繰り返し上演されるようになったという(参考文献⑥、⑨2頁、⑩136頁)。
本作の元々の長さは8巻(参考文献⑤739-740頁)もしくは10巻(参考文献③、④)と伝わるが、元素材はいくつかの場面の断片が物語の流れに沿ってまとめられたものである。柳川春葉脚色の初演時の番付および筋書き(参考文献①、②)と比較すると、残存する場面は2幕目「川島邸客室」、3幕目「逗子不動堂」、6幕目「山科停車場」、そして大詰「片岡浪子病室」のそれぞれ一部分にあたると考えられる。なお、画面からは確認できないが、浪子の死の場面のあとにはサウンドトラックが焼きこまれたカットが含まれており、別作品の素材がつながれた可能性がある。
当時の新聞評(参考文献④)は「逗子や伊香保や靑山墓地の實寫を使ひ岩田祐吉の武夫、栗島すみ子の浪子關根逹發の片岡中將と云ふ役割で劇には見られない味が出てゐる」と、ロケーション撮影や配役に舞台とは異なる「味」があることを指摘している。女優が映画で浪子を演じるのは栗島すみ子が初めてではなかったが、本作前年の映画デビュー作『虞美人草』(松竹キネマ、ヘンリー・小谷監督)で一躍スターとなった栗島の主演が、興行的成功の大きな要因になったことは間違いないだろう。2年後に同じ監督と主演のコンビで『不如帰 浪子』が製作された。
新聞記者から劇界に入った栗島狭衣を父に持つ栗島すみ子は幼少から日本舞踊を習い、狭衣が主宰したお伽芝居で初舞台を踏んだ。父が出演した吉澤商店の映画作品に出演し、有楽座女優劇には第1期生として参加。父の旧知の田口桜村の勧めで1921年に松竹キネマに入社し、「蒲田さよなら映画」を冠した『永久の愛』(池田義信監督、1935年)を最後に退社するまで「蒲田の女王」として活躍した。夫は本作を含め栗島の出演作の多くを監督した池田義臣(池田義信)だった。共演の岩田祐吉は、新派の藤沢浅二郎主宰の東京俳優養成所出身で、1920年松竹キネマに入ると個性的な役柄もこなす二枚目として、特に栗島すみ子とのコンビで人気を呼び、同じ養成所出身の諸口十九と勝見庸太郎とともに松竹キネマ初期の男優スターとして活躍した。元素材には新派出身で吉澤商店以来の映画出演歴のある関根達発と、勝見庸太郎夫人で初期の蒲田作品では中年女性の役柄で重宝された花川環の出演場面が比較的残っているのをはじめ、最後の病室の場面では、栗島、川田芳子と並ぶスター女優だった五月信子と、宝塚少女歌劇から松竹キネマ俳優学校に入り『路上の霊魂』に出演した東栄子の姿も確認できる。「和製ロイド」と呼ばれた正邦宏と、本作が映画デビューとされる柳さく子の出演場面は元素材では確認できない。 - 時間(分)
- 21
- サウンド
- サイレント
- カラーの種類
- 染色/染調色
- 製作会社
- 松竹キネマ株式会社
- 配給会社
- 松竹キネマ株式会社
- 公開年月日
- 1922年3月9日(松竹館)
- スタッフ
- 池田義臣[監督・脚色]德富蘆花[原作]水谷文二郎[撮影]西山桂太郎、岩井三郎[装置]島田棟助、平塚不倒[背画]斉藤忠男[装飾]松村爽、久野嘉彦[照明]木全俊策[現像]南德次郎[焼付]前田秋影[スチル]玉の浦人[字幕意匠]片岡左ヱ門 [振付]
- キャスト
- 栗島すみ子(浪子)岩田祐吉(川島武男)関根達発(片岡中将)花川環(浪子乳母お幾)中川芳江(片岡夫人 繁子)鈴木歌子(川島母堂 慶子)五月信子(加藤子爵夫人 清子)東栄子(加藤令嬢 千鶴子)岡島艶子(片岡令嬢 駒子)正邦宏(千々岩)柳さく子(山木娘 おとよ)
- 映写速度
- 20
- 備考
- 元素材は、鳥羽幸信氏より受贈した染色・染調色版35mm可燃性上映用ポジフィルムを、1988年度に不燃化したカラーインターネガフィルム(フィルムストック:EK、尺長:1388フィート13コマ、423.102m)。
- 参考文献
-
①「不如帰/山上山」番付[本郷座、1908年](早稲田大学演劇博物館デジタルアーカイブ/近世芝居番付データベース)https://enpaku.w.waseda.jp/db/ [登録No.]ロ22-00054-0988
②「不如帰/山上山」筋書[本郷座、1908年](早稲田大学演劇博物館デジタルアーカイブ/近世芝居番付データベース)https://enpaku.w.waseda.jp/db/ [資料番号]ロ08-00103-0249
③浅草松竹館広告(『東京朝日新聞』1922年3月9日付夕刊)3面
④無署名「活動試寫」(『東京朝日新聞』1922年3月10日付)3面
⑤『松竹七十年史』(松竹株式会社、1964年)247頁、739-740頁
⑥柳永二郎『絵番附・新派劇談』(青蛙書房、1966年)160-162頁
⑦田中純一郎「岩田祐吉」(『日本映画俳優全集 男優編』キネマ旬報社、1979年)71-72頁
⑧田中純一郎、司馬叡三「栗島すみ子」(『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報社、1980年)271-276頁
⑨諸岡知徳「声の消長―騙られた女の物語」(『神戸山手短期大学紀要』通巻50号、神戸山手短期大学、2007年)1-12頁(関西国際大学機関リポジトリKUISs-MAPS)https://kuins.repo.nii.ac.jp/records/905
⑩後藤隆基、柴田康太郎[編著]『新派SHIMPA―アヴァンギャルド演劇の水脈』(早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、2021年)44頁、136頁 - 関連リンク
-
- 「開館滿五週年記念 大興行 (桐生能楽館 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=249980
※題名は『不如歸』表記。
- 「開館滿五週年記念 大興行 (桐生能楽館 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)