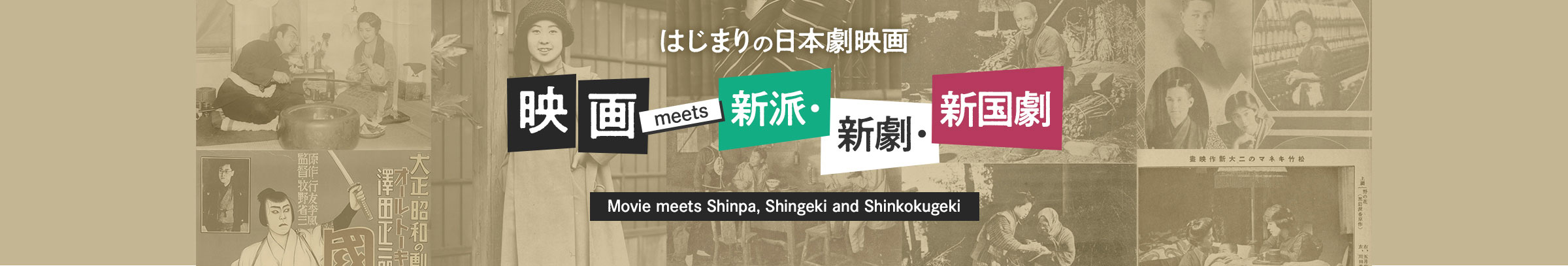國定忠次
「赤城の山も今夜を限り…」の名セリフとともに知られる新国劇の人気演目のひとつを、このタイトル・ロールの初演者である澤田正二郎の主演、「日本映画の父」牧野省三の総監督によって映画化した作品で、新国劇の過密スケジュールの合間を縫って、ロケーション撮影も含めてわずか4日間で撮られたという。短縮版ながら行友李風の原作戯曲の見せ場をほぼすべて含んでおり、稀代の人気俳優・澤正の魅力を今に伝えている。
映画詳細
- 映画題名
- 國定忠次
- 映画題名ヨミ
- クニサダチュウジ
- 製作年(西暦/和暦)
- 1924(大正13)年
- 解説
-
「赤城の山も今夜を限り…」の名セリフとともに知られる新国劇の人気演目のひとつを、タイトル・ロールの初演者である澤田正二郎の主演、「日本映画の父」牧野省三の総監督によって映画化した作品である。元素材は1928年に検閲記録の残る改訂版を基にした16㎜短縮版と考えられるが、行友李風の戯曲(参考文献⑰)と比較すると、序幕「赤城山山麓室沢村才兵衛茶屋」がないほかは、元素材の各篇は戯曲の各幕の内容にほぼ対応している。
1917年、東京新富座での旗揚げ公演が興行的に失敗した新国劇は関西で再起をはかり、京都南座を経て大阪角座で公演。立ち回りを取り入れた熱気あふれる舞台が白井松次郎の目に留まり、松竹との契約が成って迎えた夏の弁天座公演で人気のきっかけをつかむ。坪内逍遥の文芸協会演劇研究所の第2期生として学んだ澤田は、参考文献(①)によれば、新国劇創設当初に「新劇の俳優に髷物が出來るかと云つて笑はれ」たこともあるが、座付作者として行友李風を迎えて剣劇に取り組み、1919年初演の『月形半平太』と『國定忠次』が大成功を収めて新国劇=剣劇のイメージが形成されることになった。なお、『國定忠次』は立師段平が付けた最後の立廻りだったという(参考文献⑱)
1921年に新国劇は明治座で4年ぶりの東京公演を行い、そのあと劇団の夏休み中に松竹キネマで初めて映画に出演した。その作品『懐かしき力(力よ響け)』(木下杢太郎脚本・監督)は初期の蒲田作品で活躍したロシア人女優キティ・スラヴィナが共演した現代劇だった。
人気舞台俳優として映画出演の時間が取れなくなった澤田に、牧野省三が所属する東亜キネマから1924年12月の宝塚公演の機会に撮影を行うプランが打診された。同年11月13日に澤田は東上した東亜キネマ重役の立花良介と帝国ホテルで懇談して契約を了し(参考文献④)、11月下旬には仲介に関わった直木三十三(直木三十五)を同道した牧野省三が公演中の赤坂演技座の楽屋に澤田を訪ね、舞台監督の俵藤丈夫を加えた4人で会談が行われたという(参考文献③)。映画化作品については牧野側から前月の演技座公演で好評を博した『仮名手本忠臣蔵』と『月形半平太』の希望が出されたものの、最終的に『國定忠次』と菊池寛の『恩讐の彼方に』に決まったとあるが、先の澤田と立花の会談を報じた新聞記事(参考文献②)にすでに「澤正得意ものの『國定忠次』及び『恩讐の彼方』の二本を撮影する事になつたといふ」とある。11月24日に演技座の千秋楽を迎え、翌25日に大阪へ出発して当日中に到着、26日には京都入りして、27、28日に荒神山でロケーション撮影、29、30日に等持院撮影所で山形屋から忠次の臨終までのセット撮影という強行軍で(参考文献③、④)、翌12月1日には宝塚公演が初日を迎えた。同月31日に京都マキノキネマで封切、東京では翌年1月15日から浅草大東京で封切られた。わずか4日間で撮影されたことを考えれば、「映畫劇ではない。澤正一派が舞臺では十八番の「國定忠次」をその儘撮影したに過ぎない映畫である」(参考文献⑧)と指摘されることは仕方ないが、松明の光と煙が山中を満たす場面などには、ロケーション撮影による映画ならでは効果が認められよう。
なお、次の『恩讐の彼方に』は直木三十三脚色、牧野省三監督で1924年12月12日より甲陽等持院両撮影所で撮影を開始して23日完成。新国劇一座は宝塚公演を終わって帰京したと伝えられている(参考文献⑤、⑨)。同作は1925年1月29日に京都マキノキネマで封切られた。
参考文献(④)によれば、最後の捕り手との立ち回り場面で、巖鐵を演じる上田吉二郎は小砂利を集めてその上に倒れて大写しされることを申し出たが、上田の身体を気遣ってそれを認めない牧野との間に「いさかい」があったという。のちに「怪優」と呼ばれた個性派俳優の二十歳の熱血を伝えるエピソードである。
※説明および台詞字幕の少なさを補うため、以下に粗筋を添える。
「第一篇 赤城山」
飢饉と干ばつに苦しむ民のため代官を斬り赤城山に立て籠もる忠次たちを川田屋惣次が単身命懸けで訪れ、忠次を説得する。いきり立つ子分たちを制止した忠次は、自分の身柄の代わりに子分たちを助けるという条件を出す。そこに舅である御室の勘助の首を討った板割の朝太郎が戻ってくる。朝太郎の話を聞いた忠次と惣次は義理を立てて死のうとするが、様子を見ていた日光の圓蔵が割って入り、忠次一党が赤城山を下って四散することを提案して二人を納得させる。忠次は故郷と子分たちとの別れを惜しみ、愛刀義兼を月明かりにかざす。
「第二篇 山形屋」
ひとりで旅を続ける忠次は怪しい二人組の後を追う老爺に出会う。老爺は越後の農民喜右衛門で年貢のために遊女屋の山形屋藤蔵に娘を売った100両の金を、藤蔵の手下に奪われたと話す。義憤に燃えた忠次は喜右衛門の甥と偽って山形屋に入り、主人藤蔵が見くびって十手をちらつかせると初めて忠次と名乗り、100両の金に加えて娘も取り戻してふたりを帰してやる。山形屋を出た忠次は後を追ってきた山形屋の一味を斬り伏せる。
「第三篇 尼寺」
巖鉄と定八と一緒になった忠次は知り合いの尼妙眞の庵を訪ね一夜の宿を求める。快く受け入れられた3人だったが、外で妙眞が秘かに息子伊三としめし合わせているのを聞く。さらに閉じ込められていた女と赤ん坊を助け出し、彼女の話から妙眞と息子たちの悪逆ぶりを知った忠次は持っていた金を与えて女を逃がす。翌朝、庵を出る際に妙真を斬った忠次は一瞬何かに憑かれたようになるが、気を取り直して歩き始めた途端に躓いて生爪をはがしてしまう。
「第四篇 御用」
病に倒れた忠次は叔父多左衛門の土蔵の地下に匿われていたが、土蔵は与力の中山に率いられた捕り手たちに囲まれていた。子分たちの必死の抵抗もむなしく、捕り手たちは土蔵内になだれ込み、布団に横たわる忠次を取り囲む。体が不自由になった忠次を見て中山も思わず同情する。忠次は多左衛門から数珠を首に掛けられて捕縛される。 - 時間(分)
- 33
- サウンド
- サイレント
- カラーの種類
- 白黒
- 製作会社
- 東亜キネマ京都撮影所
- 配給会社
- 東亜キネマ
- 公開年月日
- 1924年12月31日(京都マキノキネマ)
1925年1月15日(浅草大東京) - スタッフ
- 牧野省三[総監督]二川文太郎、金森万象、仁科熊彦[監督]行友李風[原作]馬場春宵、曽根純三[脚色]宮崎﨑安吉、持田米彦[撮影]
- キャスト
- 澤田正二郎(國定の忠次)中井哲(川田屋惣次)上田吉二郎(清水の巖鐵)原清一(板割の浅太郎)野村清一郎(日光の圓藏)大村英男(室澤の才兵衛)鬼頭善一郎(山形屋藤藏)二葉早苗(才兵衛の娘おむめ)鳥居正(高山の定八)南吉太郎(妙眞)久松喜世子(長五郎女房お縫)橘光造(向疵の伊三)草間實(八州与力 中山清一郎)
- 検閲番号等
- 初公開は1925年7月1日からの内務省による全国統一の検閲制度実施以前だが、検閲時報にはその後の検閲記録が確認できる。
1926年
11月12日、A8980、日、時、人、正、國定忠次、9巻、2424m、東亞キネマ株式會社(製作者、申請者とも)、再
1927年
3月22日、B4013、日、時、活、正、國定忠次、10巻、2360m、東亞キネマ株式會社(製作者、申請者とも)、再
1928年
8月17日、C8520、日、時、人、正、改訂國定忠次、7巻、1891m、東亞キネマ株式會社(製作者、申請者とも)、新
同日に同題名のフィルムの検閲記録が上記を含め3件、8月18日と20日にそれぞれ2件ある。
1935年
3月16日、J3440、日、時、人、正、〔發聲フイルム式〕國定忠治、5巻、1068m、東亞キネマ株式會社(製作者)、齋藤彌仁(申請者)、新 - 映写速度
- 16
- 備考
- 元素材は、2006年度に鳥羽ツユ子氏より受贈した鳥羽幸信氏旧蔵の16mm不燃性上映用ポジフィルム(フィルムストック:不明、尺長:792フィート21コマ)。
元素材には「ホーム・ムービース・ライブラリー」のタイトルが出てくることから、これは1929年に同ライブラリーで再編集の上、4篇に分けて発売および貸出が開始された16㎜版と考えられる(参考文献⑬)。「ホーム・ムービース・ライブラリー」はイーストマン・コダック社の「コダスコープ」などの16㎜映写機所有者のために、「米國コダスコープ・ライブラリー」の日本総代理店となった大阪の深田商會が設立した映画配給機関で(参考文献⑳)、1929年には35㎜から16㎜に縮小できるプリンターを輸入したことで、国内のニュース映画、教材映画、劇映画の16㎜版を製作してカタログを充実させていった(参考文献⑮)。1934年版の目録(参考文献⑭)で16㎜版『國定忠次』は、第一篇から第四篇まで作品番号9006番から9009番までが振られており、各篇とも長さ200フィートで賃貸料1円、販売価格は目録の凡例の記述から1フィート「金14錢或は金13錢」が適用されたとみなされる。目録上での4篇の合計尺数は800フィートのため、元素材はこの16㎜版としてはほぼ完全版と考えられる。また、メインタイトルに「改訂」とあることから、この16㎜版の基になったのが1928年に検閲記録の残る『改訂國定忠次』だった可能性が考えられる。 - 参考文献
- ①澤田正二郎『苦鬪の跡』(新作社、1925年)132頁(国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/pid/982368/1/78
②無署名「映画界 ▲澤正の映畫」(『讀賣新聞』1924年11月16日付)9面
③無署名「キネマ便り 映寫幕の前に澤正が立つ迄」(『東京朝日新聞』1924年11月21日付)5面
④眞澄幹之助「『澤田と其一黨』と提携とその前後」(『東亞畫報』第三卷第一號、1925年1月)10頁
⑤編輯部「新春を飾る近作の紹介 甲陽撮影所 恩讐の彼方」(『東亞畫報』第三卷第一號、1925年1月)12頁
⑥大東京広告(『都新聞』1925年1月15日付)9面
⑦ロイド眼鏡「澤正の映畫 『忠次』を見る」(『讀賣新聞』1925年1月17日)5面
⑧山本綠葉「主要映画批評 國定忠次」(『キネマ旬報』第百八十三號、1925年1月21日)17頁
⑨編輯部「一月を飾る近作の紹介 等持院撮影所 其の他」(『東亜画報』第三巻二月号、1925年2月)11頁
⑩二川文太郎「澤正映畫一寸覺え書」(『等持院』創刊号、1925年4月)56-57頁
⑪『大正十四年 八月狂言 繪本筋書』(帝國劇場、1925年8月、立命館大学アート・リサーチセンター所蔵)ARC番付ポータルデータベース)https://www.dh-jac.net/db1/ban/search_portal.php [資料番号]arcBP02-0010-16-11
⑫「家庭用映畫の配給機關 ホーム・ムーヴィース・ライブラリー 十六ミリ映寫機所有者のために」(『映畫敎育』第二輯、1928年4月)29頁
⑬「新映畫紹介(その二) 十六ミリ映畫」(『映畫敎育』第十七輯、1929年7月)23頁
⑭『ホーム・ムービース・ライブラリー 16ミリ映畫總目錄 1934年版』(ホーム・ムービース・ライブラリー、1933年)凡例、83頁
⑮浜芳郎「加藤豊さんの思い出」(『視聴覚教育』第21巻第10号、1967年10月)121頁
⑯千葉伸夫、市橋才次郎「澤田正二郎」(『日本映画俳優全集 男優編』キネマ旬報社、1979年)257-258頁
⑰行友李風『極付 國定忠治』(『行友李風戯曲集』演劇出版社、1987年)113-165頁
⑱沢田正二郎、行友李風他「思い出座談会」(『行友李風戯曲集』演劇出版社、1987年)302-305頁。初出の雑誌『新国劇』は未確認。
⑲小松弘「澤田正二郎と映画」(児玉竜一[監]、羽鳥隆英[編]『寄らば斬るぞ! 新国劇と剣劇の世界』早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、早稲田大学演劇映像学連携研究拠点、2014年)30-36頁
⑳福島加奈子『混淆する戦前の映像文化—幻燈・玩具映画・小型映画』(思文閣出版、2022年)343-347頁 - 関連リンク
- 「(キネマ倶楽部 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)
https://nfajfilmheritage.jp/object?id=250544
- 「(キネマ倶楽部 特集プログラム・チラシ)」(映画遺産 ―国立映画アーカイブ映画資料ポータル―)