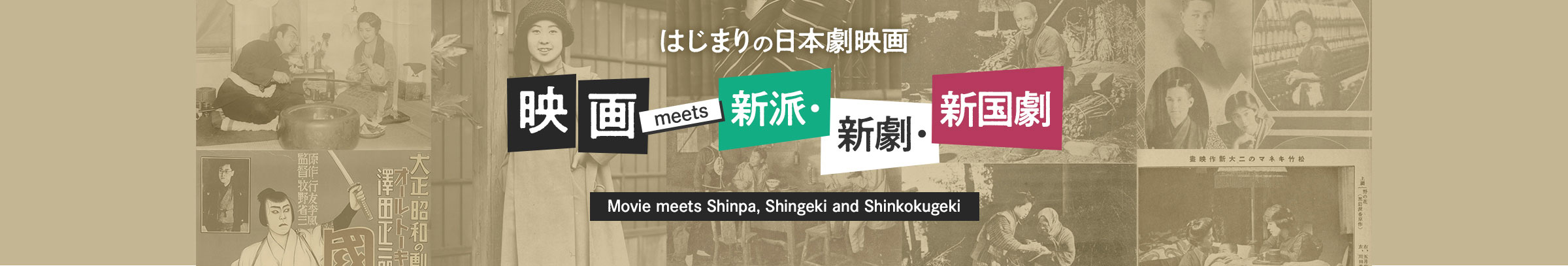社會教育劇 街の子
関東大震災の被災状況の撮影で知られ、諸官庁、公共団体、企業などから宣伝映画の制作や各種の撮影を受けていた東京シネマ商会は、一方で劇映画の監督を招いて教育劇映画を積極的に製作し販売していた。不良少年の更生を描いた本作は同社の教育劇映画の代表作といえる。日活の現代劇映画でスターになる前の夏川静江が主演し、大正後期から昭和初期の新劇史にその名を残した伊澤蘭奢をはじめとして、監督の畑中蓼坡が率いていた新劇協会の所属俳優たちが子役たちをサポートしている。
映画詳細
- 映画題名
- 社會教育劇 街の子
- 映画題名ヨミ
- シャカイキョウイクゲキチマタノコ
- 製作年(西暦/和暦)
- 1924(大正13)年
- 解説
- 芹川政一が創設した東京シネマ商会は、関東大震災発生直後の被災状況を撮影したことをきっかけに文部省社会教育課から『關東大震大火實況』の製作を委託され、その後は諸官庁、公共団体、学校、企業などから宣伝映画の制作や各種の撮影を受ける一方、教育映画を自主製作し販売していた。本作のような社会教育を目的とした劇映画の監督には、村田実や帰山教正、山根幹人、小澤得二といった当時の新進監督たちに加え、吉野二郎や細山喜代松などベテランの監督も起用されている(参考文献⑤)。
本作には、大正後期から昭和初期にかけての短い期間に活躍し、新劇史にその名を残した伊澤蘭奢が出演している。蘭奢は夫と息子と別れて故郷津和野から上京して上山草人の近代劇協会に入った。近代劇協会解散後、アメリカ帰りで本作の監督でもある畑中蓼坡の新劇協会設立に参加。畑中が国際活映株式会社(国活)に招かれて劇団活動が停止すると蘭奢は松竹キネマに入り、本名に近い三浦しげ子の芸名で映画に出演した。そののち畑中が新劇協会を再開すると復帰し、チェーホフの『桜の園』のラネーフスカヤ夫人などを演じて劇団の中心女優として活躍するが、1928年に急逝して新劇協会は翌年解散した。さらなる活躍が期待される中で突然の死を迎えた蘭奢の生涯は、夏樹静子による評伝『女優X 伊沢蘭奢の生涯』(文藝春秋、1993年)とそれを基にした舞台やドラマ、それに朝井かまての小説『輪舞曲』(新潮社、2020年)で描かれるなど、いまだに人を惹きつけている。演劇評論家の尾崎宏次は、川上貞奴、松井須磨子、森律子らが登場した日本における女優の黎明期と、関東大震災後に築地小劇場が設立されて田村秋子、山本安英、それに東山千栄子、村瀬幸子、杉村春子、岸輝子といった女優が輩出した時代のあいだをつないだ女優として「まだようやく育ちかけていた水谷八重子や夏川静枝であったというよりは、花柳はるみと伊沢蘭奢であった。」、「はるみと蘭奢は、ぐうぜんその時期にいあわせたということではなくて、演劇運動をつなぎわたす役目を果したということで、歴史からこぼしてしまうことのできない女優であった。」と、2人の女優を演劇史に位置づけている(参考文献⑧)。
主演の夏川静江(夏川静枝)とその実弟でスリの親分の息子を演じた夏川大吾(夏川大二郎)には、純映画劇運動の実践作品『生の輝き』(帰山教正監督、1919年)など、本作以前にすでに映画出演の経験があった。本作のあと、静江は演劇活動を経て日活大将軍に入ってスターの道を歩み、大吾は監督見習いとして日活太秦に入ったのち俳優に転向してやはり人気俳優となった。参考文献(⑬)によれば、当時の小石川区小日向水道町にあった東京シネマ商会の隣に夏川の家があったことが2人の出演につながったという。本作には監督の畑中が率いた新劇協会がユニットとして出演し、子役たちをサポートしている。山田博士を演じた奥村博史は平塚らいてうの夫で、画家、工芸家としても知られるが、蘭奢と同じく新劇協会創立以来のメンバーで、畑中が国活を退いた後に劇団再開のきっかけをもたらした人物だったという(参考文献⑥117頁)。スリの親分夫婦を演じた小杉義夫(小杉義男)と高橋豊子(高橋とよ)は、戦後も多くの映画に出演した名脇役として日本映画ファンにはお馴染みの俳優たちだが、本作では演劇活動に専念していた若き日の姿を見ることができる。主要な出演者の中で、もうひとりの主人公仙吉を演じた小島勉については経歴などが分からない。すでに俳優らしい演技を見せる夏川静江と、器用ではないが目に独特の表情を見せる小島の演技の対照は印象的である。
撮影は1924年6月から8月にかけて行われ(参考文献⑨)、セット撮影は高田馬場にあったという撮影所が使われたと考えられる(参考文献⑬)。ロケーション場所では、仙吉が新聞売りをする東京駅丸の内側の広場や、物語の後半で仙吉が納豆売りを思いつく場面の「改代町」と彫られた狛犬の台のある神楽坂の赤城神社境内などが確認できる。スローモーションや多重露光の手法が使われる仙吉の夢のシークエンスにも特徴があり、スポークン・タイトルを含む中間字幕を多用するなど、弁士の説明がなくとも物語を追うことができる映画劇作品として作られている。
クレジット上で「サアストン『少年僧正』より取材」と表記される原作は、1911年に翻訳出版されたサアストン(アイダ・トレッドウェル・サーストン Ida Treadwell Thurston)『少年僧正』The Bishop’s Shadow(1899)で、訳者碧川紅雨(碧川企救男)は映画キャメラマン碧川道夫の実父である(参考文献①、⑮)。 - 時間(分)
- 51
- サウンド
- サイレント
- カラーの種類
- 白黒
- 製作会社
- 東京シネマ商會
- スタッフ
- 畑中蓼坡[監督]サアストン[原作「少年僧正」より取材]野村愛正[脚色]白井茂[撮影]橋口壽志[字幕]
- キャスト
- 夏川静江(少女 お京)小島勉(不良少年仙吉)小杉義夫(スリの親分金平)髙橋豊子(仝妻 おろく)夏川大吾(仝伜 勘一)一色久子(家政婦 榮子)奥村博史(山田実博士)伊澤蘭奢(仝夫人)
- 検閲番号等
- 元素材には検閲番号の穿孔跡があり、以下の検閲時報の記録と合致する。
1931年7月6日
F7462、日、現、人、正、街の子、5巻、1216m、東京シネマ商會(製作者)、文部省(申請者)、免
元素材はメートル換算で1157.051m。 - 映写速度
- 20
- 備考
- 元素材は、1971年度に文部省より管理換された35㎜不燃性デュープネガフィルム。(フィルムストック:FUJI 1965-JM、尺長:3796フィート10コマ)。
元素材の冒頭に掲げられる「文部省推薦映畫」の証書に「大正十三年十一月二十七日 推薦」とあることから、1924年内の完成であることが確認できる。 - 参考文献
- ①サーストン[原著]、碧川紅雨[譯述]『少年僧正』(内外出版協會、1911年)(国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/pid/896951
②「社會敎育劇 街の子 東京シネマ商會作品」(『活動倶樂部』第七卷第九號、1924年9月)105-107頁
③「街の子」(『敎育映畫目錄』都商會敎育活動寫眞部、1927年)50-52頁
④「街の子」(仲木貞一『敎育映畫物語』小學生全集第七十七巻、興文社、文藝春秋社、1928年)口絵、224-228頁
⑤『特選敎育映画集』(東京シネマ商會、1932年)
⑥戸板康二『対談日本新劇史』(青蛙書房、1961年)109-124頁
⑦田中栄三『明治大正新劇史資料』(演劇出版社、1964年)
⑧尾崎宏次『女優の系図』(朝日新聞社、1964年)171-199頁
⑨「作品解説/街の子」(『東京国立近代美術館 フィルムセンター所蔵映画目録Ⅰ 日本劇映画』、1976年)10-11頁
⑩吉田智恵男、市橋才次郎「伊澤蘭奢」(『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報社、1980年)66-67頁
⑪吉田智恵男、司馬叡三「夏川静枝」(『日本映画俳優全集 女優編』キネマ旬報社、1980年)494-496頁
⑫戸板康二『物語近代日本女優史』(中央公論社、1980年。文庫版は1983年)84-92頁[文庫版]
⑬白井茂『カメラと人生―白井茂回顧録―』(ユニ通信社、1983年)38-40頁
⑭『平塚らいてうの会紀要』第2号(平塚らいてうの会、2009年)
⑮「碧川, 紅雨, 1877-1934」(Web NDL Authorities 国立国会図書館典拠データ検索・提供サービス)https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00507903