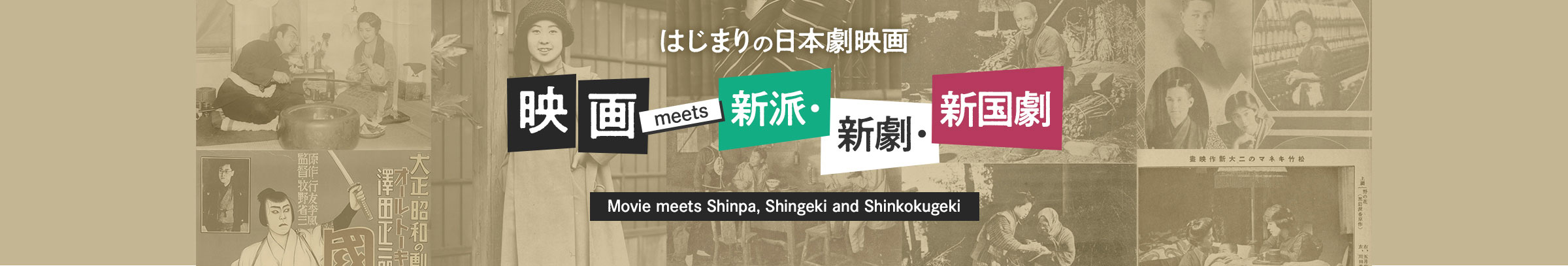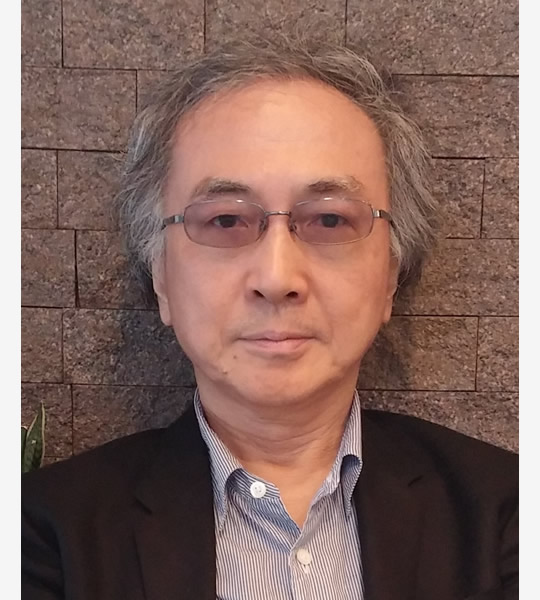映画 meets 新派・新劇・新国劇 総論
近代日本演劇と映画―顔・スピード・台詞
1 「顔」のイメージ・女方から女優へ
我々は過去の思い出の俳優を回想し、或いはこれから見る舞台を想像する。
だが、それは「伝統的古典芸能」であろうと「前衛的尖端芸術」であろうと、無意識の内に、電気照明を用いた舞台や俳優を思い浮べる。
つまり、現代演劇は基本的に電気照明の所産であり、我々の視覚も電気により規定されている。俳優の顔を想像し、思い出す際に写真や映像のそれを自明のようにイメージする。
写真や映像に我々の目は捉えられているのだ。
かつては、役者絵の見立て絵や、小説ではその挿絵の架空の人物の顔が、大きなイメージを作っていた。
初期劇映画は、題材に各国の文化的記憶に応じて観客が図像的に直感し易い世界や人物が選ばれることもあった。日本では歌舞伎、新派が圧倒的に多いが、重要なのは、映画で公開される役者の「顔」が、元来多様であったはずの役のイメージを規定してしまう過程である。これは歌舞伎以上に、初期映画に極めて重要で密接な影響を与えた新派に相応しい。
『不如帰』の浪子や『金色夜叉』のお宮のイメージは、私などは初代水谷八重子の舞台の記憶と直結するし、資料で見ても、挿絵や写真に残る木下吉之助や木村操の美貌で想起する。
しかし、明治大正期の多彩な劇団の跋扈した新派で、それらの舞台を実見できた観客は都市部の限られた存在だった。地方廻りの新派の劇団のお宮や浪子は、それこそ、美貌と程遠いかなりの容貌の女方が普通に演じていた。
だが、映画の一般化によって、かなり辺鄙な地域でも都市でも、立花貞二郎や衣笠貞之助のような美貌の女方や『ほとヽぎす』の栗島すみ子のような女優の「顔」が全国に流通するようになると、従来の旅廻りの劇団のお宮や浪子は、最早違和感を持たれ、或は珍品扱いされてしまう。
舞台では極めて多様だったある役のイメージを、映画による画一的な「顔」の定着が規定し、決定する役割を果す逆転現象が起きる。元来はどこにも実在しない浪子の顔に、「こんな顔ではない」という拒絶感を観客が抱くに至るのだ。
新派も、昭和初期に新劇出身の初代水谷八重子が出演するようになり、女優が徐々に女方に代る。『寒椿』の原作小島孤舟『湖畔の家』は新派の演目で、まだ女学生だった水谷は舞台出演の際の退学騒ぎから「覆面令嬢」として出演し、新宿十二社にあった撮影所に通った。畑中蓼坡監督とは芸術座時代の親交があり、畑中同様、水谷も5年後、米国へ映画視察を行い、著名監督、俳優と会い、話題になった。
昭和初期に川口松太郎が新派に関係を深めたのも大きい。泉鏡花や真山青果の台詞を張るような女方の調子から、川口の日常的でヴィヴィドな台詞に移行する。トーキーでの『上陸第一歩』などの水谷の掠れ声は切迫感があるが、声(台詞)との連動も女優が一般化する要因の一つだった。演劇・映画雑誌も、1924年には『映画と演芸』と逆転した名称もあり、観客の目の記憶でも舞台より映画が先行する世代が登場する。
多くの著名作が映画化された歌舞伎でも、映画の主人公のイメージを歌舞伎の舞台に反影させて見た観客は少なくない。ある世代の人々は、大石内蔵助というと映画・テレビの長谷川一夫や八世松本幸四郎(初代白鸚)の輪郭や姿形や声音を未だに連想する。近代の複製技術があるイメージを一般化、普及すると共に、画一化してしまう利点と弊害も指摘される。
新派と映画の重要な関係は、映画史で多く論じられるが、こうした「顔」のイメージを舞台と映画の観客の視覚と記憶の重層のなかで考えるのも意味があるだろう。
2 スピードの時代
初期映画での立回り(タテ)は、映像的には、実際のタテの間やテンポと違うのは想像できる。また、映画館では和洋様々な音楽入りだろうが、撮影時はどうしていたのだろうか。歌舞伎でも、附立という下座音楽入りの稽古までは、立師が口で調子を取りつつ行うから、できない訳ではないけれども。
ただ、連鎖劇で著名な山崎長之輔のタテでも、間は歌舞伎調にゆっくりしたものだったようだ。新国劇文芸部の仲木貞一は、こう書いている。
「従来山長[山崎長之輔]にしろ誰にしろ皆悠長なセリフ廻しで、のろのろした動作をしていたのに、彼[澤田正二郎]の一座は元気に任せて電光石火のような動作をする。セリフを云うにも喧嘩のようにガミガミと強く速く云う。これが当時の見物の気に入ったのである。時宛も欧州大戦で好況の最絶頂の時で、気が立っている。従ってピッチの早い物がピタリ気持に合うのである。大阪計りが然うではない。この大戦期を境として、東京でも何処でも都会地では、この速いテンポの物でなくては客に喜ばれなくなった」
ドンタッポの鳴物、千鳥の合方での型を踏まえての悠長な動きによる身体機能を転換し、スピード感を強調したのが、新国劇では「殺陣」と表記する立回りの真髄だった。
それが「欧州大戦で好況の」血の気の多い時代には、合っていたのだ。
『国定忠治』小松原の場の殺陣は、澤田正二郎の映画より、舞台で見た新国劇の辰巳柳太郎や大山克己らの方がスピードが速いのは、舞台と映画の表現システムの違いに拠るのだろう。
『決闘高田馬場』は歌舞伎では七世澤村訥子の得意芸で、その迫力は「花道を三歩半」で入ると神話化された。映画『高田馬場』の澤田正二郎は当時の撮影技術のためか疾走シーンがないが、『血煙高田の馬場』で阪東妻三郎が銀幕の中で走りまくる生動感や凄味に接すると、「スピードの時代」に、演劇は映画に敗北する運命だったと痛感する。
後に歌舞伎の立師・坂東八重之助は、阪東妻三郎『雄呂地』のタテを『義経千本桜』小金吾の立回りに応用したと述べるが、今ではそれが「古典歌舞伎」の立廻りとして定着している。映画と演劇の相関作用として興味深い。
3 声と台詞
1924年に旗揚げした築地小劇場がそれまで多様だった「新劇」を禁欲、前衛、深刻、純粋というイメージにしてしまったが、それがラジオの放送開始や映画のトーキー化の時代でもあったことは、重要である。
トーキー化に際しての様々な事態や問題は、幾つかの映画や演劇作品でも扱われ、話題になる。台詞を言える俳優も、歌舞伎、剣劇、節劇、女芝居等出身の違う各優が勝手に台詞を喋るのでかみ合わなかったという。
そこで、「台詞が言える」新劇俳優の存在が役立った。
「新劇俳優」というと一般には「標準語」を話す俳優のイメージだが、「築地小劇場」以前、明治末から大正期までの「文芸協会」「芸術座」系や「近代劇協会」「新劇協会」系の新劇の演技や台詞は随分違ったものと推測される。当時の音盤の録音技術は、1930年代以降のマイク型と異なり、実際の発声や速度とは違うというが、松井須磨子の台詞などは「築地」系とは別物である。また、「近代劇協会」の上山草人の極めて訛りの強い台詞を映画で聞くと、こうした俳優たちが『ファウスト』を演じたのが、大正初期の新劇なのかと痛感することがある。築地系でも青山杉作、新派の井上正夫の訛りなども印象的で記憶に残る。
杉村春子は晩年まで広島訛りを気に懸けていたという。歌舞伎でさえ著名俳優の何人かが名古屋出身で、逆に訛りが口伝として伝わるという、強度の魅力さえあった。東京下谷生れの田村秋子が新劇入りに際して、父親の田村西男が「娘は訛りがありませんが新劇俳優になれるでしょうか」と問うたという「伝説」も満更作り話ともいえない。
逆に、台詞に特異な訛りや癖があるスターも少なくない。
大河内傅次郎はよく知られる独特の調子に魅力がある。富士正晴によると、大河内は新国劇に居た舞台出身なので「マイクを通すと非常に聞き辛いが、素の場合には朗々としてよく徹る」という。
俳優の声の魅力は、台詞の意味の明瞭度と一致しない。「台詞はよく解らないが人気が継続する系譜」は舞台、映画からテレビまである。大河内や晩年の片岡千恵蔵、田村正和まで、意味は聴き取り難くとも、その声を真似したくなる魅惑に吸引される。台詞の解り易い俳優は幾らも居ても、その持ち役は彼等でなくては観客は満足しないのだ。
また、台詞の速度も、表現主義の影響を受けた「築地」では、違ったようだ。
旗挙げ公演のゲオルグ・カイザーの『海戦』では、「恐ろしいスピード(セリフは大部分何を言っているのか聞き取れなかった)絶叫(従来の発声法を無視していた)直線的な烈しい動き(それはいままでのどんな歌舞伎的、新派的、新劇的な身のこなしとも全く違っていた)」と村山知義は言う。
帝劇女優劇から築地小劇場へ移った高橋とよは、築地に入りその台詞の速度に驚き、戸惑ったという。カイザー『朝から夜中まで』は、「私の演技は間延びがして(略)気がついたときはもうおそくて、ちょうどエスカレーターに乗りそこなった」感じだった。「表現派的演技というのは一人の俳優が終始しゃべっているように、ほとんど間をおかずに次から次へと芝居が進展し、転換されてゆく、こういう演出の手法でありましたから、帝劇のよう(略)ではテンポに追いつ」けなかったと高橋は『沸る 自伝随筆』で回顧する。
新劇調と言われる「物言う術」や勿体ぶった台詞がいつから定着したかは詳らかにしない。
新劇でも現在語られるのは、最後まで「ひとすじの道」を歩んだ築地系の立派な俳優達であり、そこから「脱落」した俳優たちは看過される。
『桜の園』のラネーフスカヤは東山千栄子がモスクワ在住経験のため神話化されるが、芦原英了、大岡昇平の世代は異口同音に、それ以前に「新劇協会」で見た伊澤蘭奢の記憶があるので落胆したと書く。確かに、あの役は東山が体現し前景化してしまう母性のイメージとは全く異なる。「新劇協会」「近代劇協会」の女優たちは蘭奢、山川浦路に衣川孔雀と、美麗絢爛で「玄人」風な官能と遊戯性を備えた芸名であり、築地小劇場以後の本名の多い「新劇俳優」の地味な感じとは異質だった。『社會教育劇 街の子』で蘭奢を見られるのは嬉しい。
『收穫』の花柳はるみも、築地小劇場でラネーフスカヤを演じているが、新劇史では触れられない。花柳はるみは大岡昇平も飯島正もファンで、官能的な魅力があったという。
築地出身でメインストリームから外れ、正に「外道」を行ったのが、女侠物の映画や実演で売った伏見直江で、彼女が『三人姉妹』のイリーナを演じたのが信じられない。漢字もあまり読めない伏見の新劇女優としての魅力ある挿話は富士正晴や千田是也が書いている。
こうしてみると、演劇と初期映画の関りは、後に「本流」から脱落したクセの強い俳優の方に特徴が滲み出ていると思える。