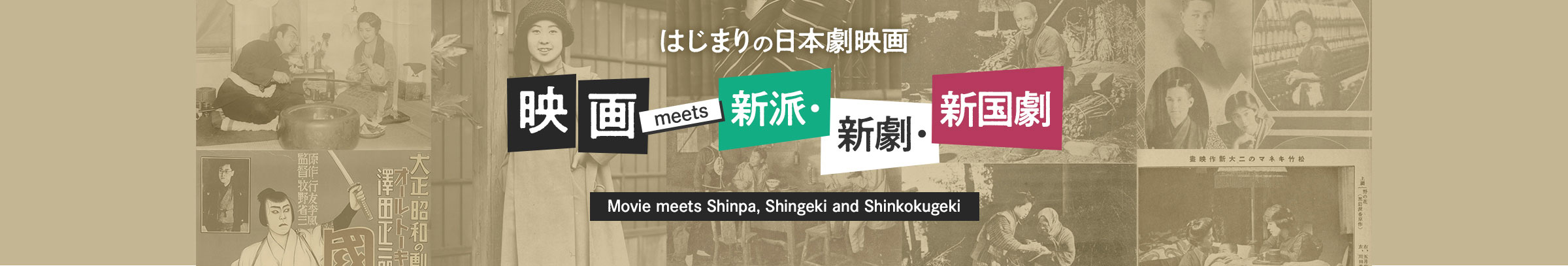映画 meets 新劇
素人の時代 ――初期の映画と新劇界――
明治維新を境にして、演劇面でもその前後で大きく変わった。女優誕生がその一つで、新しく生まれた演劇や劇場があったことがもう一つ、そしてそういう変革を担って促進したのが、素人だったということである。
幕末から明治の初頭にかけて、海外視察団が数度にわたって派遣されたが、彼らは彼の地で劇場に招かれ、観劇するのが常だった。こうして痛感したのは演劇を取り巻く環境が、わが国の現状とはまったく違うことだった。
使節団の見聞から西洋近代をモデルにした「脱亜入欧」が国策になり、新政府としてはあらゆるものの「改良」が急務になった。その一つに「演劇改良」があり、西洋式の劇場の建設や新脚本の創造や、女優の誕生を促すことが緊急の課題として浮上した。これに応えたのが政治青年や学者や財界人、つまりは演劇の素人だった。
自由民権運動に身を挺していた川上音二郎が、その趣旨を込めたオッペケペー節を謳いはじめたのが明治10年代で、やがてより効果のある手段として選んだのが演劇だった。同20年代に川上らが創造した演劇、これを新演劇と呼び、その担い手を新俳優と称したが、続々と生まれた彼らと川上が異なるのは、明治26(1893)年に単身で渡仏して以来、川上が数回にわたって一座を率いて欧米巡演をしたことである。この間に妻の貞奴を女優としてデビューさせ、いち早く欧米の劇界の実態を知った。これが川上をしてわが国初の、女優養成に着手させた背景だった。すなわち川上貞奴を所長にしての、明治41(1908)年9月に開所した帝国女優養成所。これは建築計画が進められていた帝劇こと帝国劇場に引き継がれて翌年に帝国劇場附属技芸学校と改称したが、この動きをバックアップしたのが渋沢栄一らの財界人で、彼らが東京・日比谷の一画に明治44(1911)年に新築・開場したのが、本格的な西洋式の劇場、帝劇だった。客席はすべて椅子席で額縁舞台を設置し、劇場付きの芝居茶屋を廃してチケット制を採った。劇場の制度も素人が変えたのである。
開場年の5月から、この劇場特有の「女優劇」が始まった。これを支えたのが技芸学校の卒業生で、したがって彼女たちは「帝劇女優」と呼ばれた。このうち6期生の高橋とよ(当時は豊子)は、戦後、映画の名脇役として小津安二郎監督らに重用された。
「帝劇女優」の活躍に刺激されて、明治41(1908)年の年末に、全椅子席の高等演芸場としてオープンした有楽座が同45(1912)年に女優劇を開始、その1期生の中に栗島すみ子がいた。すみ子は舞台でキャリアを重ね、映画の製作に乗り出した松竹が大正9(1920)年の2月に松竹キネマ合名社を設立して6月に蒲田撮影所を開設すると、翌年2月にここに入った。第1作はアメリカ帰りのヘンリー小谷が監督・脚色・撮影した『虞美人草』(鈴木善太郎原作、大正10[1921]年4月封切)で、すみ子はこの一作で映画女優のスター第1号になった。
この映画ですみ子と共演した岩田祐吉は、新派俳優の藤沢浅二郎が明治41(1908)年11月に開所した東京俳優養成所(同43[1910]年に東京俳優学校と改称)の1期生だった。音二郎の要請から男優の養成を専門にしたが、ここの関係者の多くが初期の映画に関わった。
講師に小山内薫や桝本清らがいたことから、生徒は新劇を目指しはじめた。上山草人、田中栄三、諸口十九、勝見庸太郎らのメンバーで、中での変わり種が草人である。
ここを出て文芸協会の演劇研究所に入り、その劇団員になったものの喧嘩沙汰で退会させられた草人は――この名は田舎者やカカシを意味する俳号――、伊庭孝や妻の山川浦路らとともに明治45(1912)年に近代劇協会を立ち上げた。ゲーテの『ファウスト』(森鷗外訳)やチェーホフの『桜の園』(伊東六郎訳)などを本邦初演して一時気を吐いたものの次第に力を落とし、大正8(1919)年に夫婦ともども夜逃げ同然に渡米し、ロスアンジェルスに流れ着くと、草人はハリウッドのエキストラになった。早川雪洲が日本人スターとして活躍していたころである。
やがてダグラス・フェアバンクスが『バグダッドの盗賊』(ラオール・ウォルシュ監督、1924年)の製作に際してモンゴルの王子役を探していると聞いた草人は、オーディションを受けて、その役を射止めた。以後、草人は雪洲に次ぐ日本人スターとして40本近くのハリウッド映画に出演した。が、トーキーの時代になって不安を覚え、浦路と別れて帰国すると、昭和6(1931)年に松竹蒲田の人になった。ところが企画に恵まれず、その後は鳴かず飛ばずに生涯を終えた。
東京俳優養成所出身のもう一人の異色は田中栄三で、田中は監督として大活躍した。
卒業後、田中は有楽座の専属劇団たる土曜劇場などで新劇の舞台を踏んでいた。一方、桝本は大正元(1912)年創立の日活に入社し、呼び寄せたのが田中だった。田中は7カ月ほど助手として働き、同7(1918)年に監督になった。第1回作品が『暁』(岡本綺堂原作)で、これには川上一座の座員として、欧米を巡業した山本嘉一が出演していた。田中はその後日活向島撮影所を代表する監督として新派映画の「革新」を進め、女形に代わる女優を起用しつつ、50本に余る映画を撮った。
わが国で3番目の、そして男女共学としては最初の俳優養成所が、明治42(1909)年に早大教授坪内逍遥が監督に就任して開設された文芸協会の演劇研究所だった。1期生の中に佐々木積(女優の夏川静枝の養父)や松井須磨子や山川浦路らがいて、開所にやや遅れて上山草人らが入所、2期生の中に澤田正二郎、倉橋仙太郎、林千歳らがいた。須磨子は明治44(1911)年に『人形の家』(イプセン作)のヒロインを演じて新劇女優の第1号としてその存在を社会的に認知させ、澤田は芸術座を経て大正6(1917)年に新国劇を創立すると、劇界に一大旋風を巻き起こした。
澤田は40年に足らない一生の中で、5本の映画を残した。最初が松竹蒲田の『懐かしき力』(佐々木杢郎脚本・監督、新国劇のユニット出演、大正10[1921]年封切)で、次いで東亜特別作品として『國定忠次』(行友李風原作、牧野省三総監督、大正13[1924]年封切)と『恩讐の彼方に』(菊池寛原作、直木三十五脚色、牧野省三監督、大正14[1925]年封切)を撮った。人気沸騰中の澤田とあってギャラの折り合いがつかず、一時間いくらという前代未聞の時間制の出演料で契約しての、早撮りだった。
澤田の盟友・倉橋仙太郎が総監督として大正14(1925)年に結成した第二新国劇に、室町次郎なる俳優がいた。が、旅回りの悲哀を感じて退団し、同15(1926)年8月に日活大将軍撮影所に入社、同時に芸名を大河内伝次郎と改めた。第一回主演作が『長恨』(伊藤大輔脚色・監督、大正15[1926]年封切)で、翌年の『忠次旅日記』三部作(伊藤大輔脚色・監督)で早くもスターの座に就いた。その代表作が日活太秦の『新版大岡政談』三部作(林不亡原作、伊藤大輔脚色・監督、昭和3[1928]年封切)だ。大河内とコンビを組んだ伏見直江は築地小劇場の出身で、無筆の直江に字を教えたのが、ここの中心人物で、演出という仕事を確立した小山内薫だった。
前記の近代劇協会で女優としてのスタートを切った伊澤蘭奢は、上山草人が渡米に際して身柄を畑中蓼坡に預けた。
畑中は13年余にわたるアメリカでの生活中に、ニューヨークの演劇学校で学んだように俳優を目指していて、帰国して芸術座に入った。大正7(1918)年のこと。が、翌年の正月公演『カルメン』(メリメ原作)のヒロインを演じていた須磨子が、前年の11月にスペイン風邪で急死した愛人で先生でもあった島村抱月の後を追って自殺し、芸術座はたちまち解体した。そこで蓼坡が結成したのが新劇協会で、当然ながら蘭奢はここに身を置き、大正8(1919)年の旗揚げ公演『叔父ワーニャ』(チェーホフ作)に出演した。ところが同じ年、蓼坡は誘われて国活(国際活映)に監督として入社し、新劇協会はしばらく活動を休止した。このこともあって同年に蓼坡が演出した『青い鳥』(メーテルリンク作)は民衆座を名乗ってのものだったが、チルチルを初代水谷八重子が、ミチルを夏川静江(のち静枝)が演じた舞台だった。
八重子は義兄の水谷竹紫が芸術座の理事だった関係から、その旗揚げ公演(大正2[1913]年)『内部』(メーテルリンク作)の群衆の子役に出た。時に7歳だった。次いで3年後の『アンナ・カレーニナ』(トルストイ原作)にも出演して、アンナ(須磨子)の息子セルジーを演じて正式な初舞台披露をした。それからが『青い鳥』への出演になるが、続いて蓼坡の国活作品『寒椿』(小島孤舟原作、大正10[1921]年封切)へも「覆面令嬢」を名乗って出た。この初映画の相手が新派の革新児・井上正夫で、これが運命的な出会いになって、八重子は映画や舞台で井上との共演が続き、やがて新派を背負う大スターになった。
国活は大正13(1924)年に崩壊した。このことから蓼坡は反省を込めて新劇協会を再興し、ほどなく伊澤蘭奢も再度入団してここの中心女優として活躍した。劇団が活動を休止していた間、蘭奢は同11(1922)年に松竹蒲田に入社すると、三浦しげ子の芸名で勝見庸太郎や林千歳主演の映画の、脇役を勤めた。
花柳はるみも芸術座から出発した。が、新劇女優としては目立たなかった。一躍注目されたのはヒロインを演じた天活特別作品『生の輝き』と『深山の乙女』(いずれも水沢武彦原作・脚色、帰山教正監督)が、大正8(1919)年9月に相次いで封切られたことだった。
映画の革新を目指していた帰山が新作の出演俳優の人選を友人の岸田辰弥に相談したところ、岸田が関係する踏路社という新劇団のユニット出演を持ちかけられた。会社の専属俳優などを使わず、切り詰めた予算で製作するのを決めていた帰山には渡りに船で、すぐに村田実らの出演が決まった。女優については踏路社の『春の目ざめ』(ヴェデキント作、大正6[1917]年)に客演していた花柳はるみを、村田が推した。こうして封切られた「純粋映画劇」の試みは、映画史の一つの画期になった。
ここに名を挙げた村田実は、帰山らの映画芸術協会の俳優体験を経て日活向島の監督になり(大正12[1923]年)、相次いで秀作を発表して「巨匠」と言われる最初の監督になった。
以上、概略のごとく、映画の初期に新劇関係者が多く手を貸している。ともに素人から玄人へというコースを取ったが、この両者の関係を無視しては、映画の黎明期を十分に語られないと言ってもいいのではあるまいか。