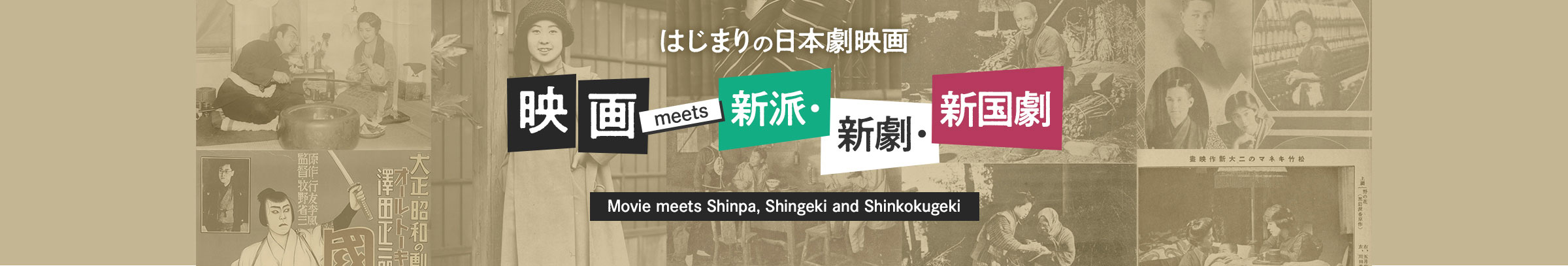映画 meets 新国劇
四散する演技術、人文情報学の新世界へ
「映画meets歌舞伎」「映画meets新派」「映画meets新劇」「映画meets新国劇」。国立映画アーカイブ『はじまりの日本劇映画』を構成する配信4種(令和7[2025]年3月現在)の内、本論に見る「映画meets新国劇」は変則と言わざるを得ない。歌舞伎、新派、新劇が各々、○○一門、○○一派、○○一党、○○団、○○座、○○劇のような様々な結社体が織り成す日本演劇史の一大類型であるのに対し、新国劇は大正6(1917)年‐昭和62(1987)年の70年間、高度の独立性を示し得た演劇界の一結社体に過ぎない。同時に、新国劇は坪内逍遙(安政6[1859]年‐昭和10[1935]年)主宰の東京・文芸協会演劇研究所に修学した新劇系役者・澤田正二郎(明治25[1892]年‐昭和4[1929]年)を座長に結団したが、澤田は歌舞伎の代表作『仮名手本忠臣蔵』も新派の代表作『金色夜叉』も自身の公演(東京・演伎座、大正13[1924]年10月/同・帝国劇場、昭和2[1927]年8月)に組み入れた。事程然様、新国劇はキメラ的結社体である。
新国劇70年史を簡単に振り返ろう。大正6(1917)年4月、澤田正二郎は文芸協会演劇研究所の同門生・倉橋仙太郎(明治23[1890]年‐昭和40[1965]年)等と新国劇を結団。幕末維新物『月形半平太』(京都・明治座、大正8[1919]年4月)、侠客物『国定忠次』(同、同年8月)に代表される迫真的な殺陣の剣劇を編み出し、近代日本社会の支持を得ると同時に、前記『仮名手本忠臣蔵』『金色夜叉』やフランス演劇『シラノ・ド・ベルジュラック』の趣向を幕末維新物の世界に託した翻案劇『白野弁十郎』(東京・邦楽座、大正15[1926]年1月)等、剣劇以外も精力的に公演するが、昭和4(1929)年に満36歳没。後継者に抜擢された座員、当時30歳前後の島田正吾(明治38[1905]年‐平成16[2004]年)と辰巳柳太郎(明治38[1905]年‐平成元[1989]年)は以後50年以上に亘り、新国劇の社会性を守り続け、結団70年公演後の昭和62(1987)年9月に座名「新国劇」を澤田家に奉還。近代日本社会の閉幕に相前後しつつ新国劇も解団した。
新国劇と日本映画史の由縁を問われ、第一に思い当るのは殺陣の視点だろう。日本映画史の通説に従えば、尾上松之助(明治8[1875]年‐大正15[1926]年)を中心に産業化した京都剣劇界が、関東大震災(大正12[1923]年)前後の映画界の一大再編を通じ、阪東妻三郎(明治34[1901]年‐昭和28[1953]年)、大河内傳次郎(明治31[1898]年‐昭和37[1962]年)等、明治後期生の花形剣劇人の繚乱期に移るに際し、新国劇の殺陣は重要な役割を演じた。「映画meets新国劇」配信中の、野外公演の記録映画である澤田正二郎主演『高田馬場』(大正13[1924]年)の大詰、主人公・中山安兵衛が叔父・菅野六郎左衛門の敵を一気呵成に倒す殺陣を、同一の状況を示す先人・尾上松之助主演『中山安兵衛』(大正14[1925]年、おもちゃ映画ミュージアム蔵)、後人・大河内傳次郎主演『血煙高田の馬場』(昭和3[1928]年、マツダ映画社蔵)の殺陣と比較すれば、松之助⇒澤田⇒大河内と殺陣の振付が高速化、不定型化する過程が想像されよう。
第二に物語の視点が思い当る。無音版14分とレコードトーキー版13分の2種が残る澤田正二郎主演『月形半平太』(大正14[1925]年、国立映画アーカイブ蔵)は、元々は新国劇の社会的支持を呼んだ剣劇であり、同時に大正期の幕末維新物の世界建築に重要な役割を演じた物語である。種本は近世文芸『春色梅児誉美』(天保3[1832]年‐4[1833]年)と言われるが [注1] 、劇作・行友李風(明治10[1877]年‐昭和34[1959]年)が仕組む防長藩同志の内ゲバ物語は実際、波瀾万丈である。自然、映画化が繰り返された。阪東妻三郎は昭和6(1931)年、大河内傳次郎は昭和8(1933)年、嵐寛寿郎(明治35[1902]年‐昭和55[1980]年)は昭和10(1935)年、月形龍之介(明治35[1902]年‐昭和45[1970]年)は昭和12(1937)年、林長二郎=長谷川一夫(明治41[1908]年‐昭和59[1984]年)は昭和4(1929)年・9(1934)年・31(1956)年、市川右太衛門(明治40[1907]年‐平成11[1999]年)は昭和27(1952)年…と、明治後期生の花形剣劇人が一様に、一度は映画『月形半平太』主演歴を持つ有様は壮観である。
無論『月形半平太』と日本映画史の由縁は直接の映画化に止まるまい。京都国際映画祭2018に上映(京都・大江能楽堂、平成30[2018]年10月)された幕末維新物の古典、市川右太衛門主演『一殺多生剣』(昭和4[1929]年、おもちゃ映画ミュージアム蔵)の開巻、旧幕臣の主人公・緒方十兵衛が自身の思想の赴くままに彰義隊入隊を拒み、評定の座を立つ場面は、原作/脚本/監督・伊藤大輔(明治31[1898]年‐昭和56[1981]年)の自覚の有無は措き、防長藩同志が主人公・月形半平太を弾劾する『月形半平太』2幕目「双林寺客殿の評定」 [注2] を連想せざるを得ない。伊藤の師は小山内薫(明治14[1881]年‐昭和3[1928]年)。澤田正二郎の師は坪内逍遙。小山内は自由劇場、逍遙は文芸協会を結団し、共に新劇=近代日本演劇の実体化に先鞭を着けた。2人の指導を受けた澤田と伊藤が、一方は演劇、一方は映画に、近代日本の建国神話に当る幕末維新物の世界建築に重要な役割を演じたのは歴史の因縁である。
第三に役者の視点を挙げたい。澤田正二郎の映画出演は「映画meets新国劇」配信中の2作(令和7[2025]年3月現在)を含む5作に止まるが [注3] 、在団中/退団後に映画出演歴を持つ新国劇座員は相当数に上る。配信中の澤田主演『国定忠次』(大正13[1924]年)主要出演者の場合、清水巌鉄役の上田吉二郎(明治37[1904]年‐昭和47年[1972]/ [図1] )、山形屋藤造役の鬼頭善一郎(明治28年[1895]‐?年/[図2] )、板割浅太郎役の原清二=原聖四郎(明治37[1904]年‐?年/ [図3] )の映画出演歴が質量共に目を引く。石山健二郎(明治36[1903]年‐昭和51[1976]年)や小川虎之助(明治30[1897]年‐昭和42[1967]年)、大友柳太朗(明治45[1912]年‐昭和60[1985]年)や黒川弥太郎(明治43[1910]年‐昭和59[1984]年)、世代は下るが、緒形拳(昭和12[1937]年‐平成20[2008]年)等も元々は新国劇座員である。島田正吾と辰巳柳太郎も度々、映画出演した。とは言え、映画の新国劇系役者の極付は畢竟、澤田と叔父甥の関係性に結ばれる大河内傳次郎だろう。
[図1] 『國定忠次』(左:上田吉二郎[清水巌鉄役])
[図2] 『國定忠次』(原清二[板割浅太郎役])
[図3] 『國定忠次』(右:鬼頭善一郎[山形屋藤造役])
大河内傳次郎の演技歴の基点は、前述の倉橋仙太郎が新国劇退団後に主宰した大阪・新民衆劇学校である。同門生に原健作=原健策(明治38[1905]年‐平成14[2002]年)等が居る。澤田正二郎と大河内を叔父甥の関係性に擬す由縁である。新民衆劇学校が発展した第二新国劇を原と共に主導した大河内が、大正15(1926)年に映画界に転じ、前述の脚本/監督・伊藤大輔と組みつつ京都剣劇界の花形に上り詰める過程は多言を要すまい。『忠次旅日記』3部作(昭和2[1927]年)国定忠次役、前述『血煙高田の馬場』中山安兵衛役、『興亡新撰組』2部作(昭和5[1930]年)近藤勇役、前述『月形半平太』月形半平太役…と、大河内は澤田の代表作を直接・間接に映画化した。尚、前田吟(昭和19[1944]年‐)も晩年の倉橋の指導を受けた役者である [注4] 。前田と原の関係性を存じ上げぬままに、『郡上一揆』(平成12[2000]年)の前田の演技に、昭和30年代の東映剣劇を彩る悪役の原を連想したのは二昔以上前の記憶である。
無論、演技的学歴と実際の演技の短絡は非学術的である。とは言え、第二新国劇を含む新国劇系役者の共通性、未体系化のままに不可視化した新国劇演技術の実体性を想像するのは牽強付会と言い切れまい。緒形拳は映画出演に際し、新国劇に起因する自身の演技の「クサ」味が+/-「半々」に働いたと語る [注5] 。緒形の言う「クサ」味が歌舞伎系、新派系、新劇系役者の「クサ」味と重なりつつも異なるのは、演劇学者・児玉竜一の『日本のいちばん長い日』(昭和42[1967]年)論の一節――新国劇系、新劇=文学座系、映画系の異種混淆的配役が如何に物語を劇的に「増幅」するか――を繙けば [注6] 、十分に腑に落ちよう。歌舞伎、新派、新劇のキメラ的結社体である新国劇が、次第に固有の演技術の「クサ」味を醸成し、映画系、歌舞伎系、新派系、新劇系役者と共に日本映画史を色付ける…。このような視点の日本文芸――文=言語的媒体と芸=非言語的媒体の総体――史が待たれよう。
新国劇は演技術を体系化し得ぬままに解団し、座員は四散した。とは言え、新国劇70年史は元々、四散の歴史である。新国劇と日本映画史の由縁を説く目的に照らせば、想定内とは言え、本論に触れた新国劇座員の内、澤田正二郎、島田正吾、辰巳柳太郎の3座長以外は退団者である。今後、人文情報学が一層の深化を見せれば、新国劇系役者が四散の最中に映画に記録させた、第一の視点に見た殺陣を含む新国劇演技術を計量化し、心有る文芸実践家と共に体系化する未来が来るかも知れない。近代日本社会の表象である新国劇の男性中心主義は肯定し得ないが、同時に新国劇――特に劇作・長谷川伸(明治17[1884]年‐昭和38[1963]年)の股旅物――が社会的弱者を主題化した点も否定し得ない。新国劇系役者は社会的弱者を如何に形象化したのか?社会に弱者が存在する以上、新国劇は現在も重要な参照項だろう。「映画meets新国劇」開幕は新国劇演技術「方法」化の第1幕と信じたい。
- 大笹吉雄『日本現代演劇史――明治・大正篇』、白水社、1985年、237頁。
- 行友李風「維新情史・月形半平太――5幕8場」、行友李風【著】/北條秀司【編】『行友李風戯曲集』、演劇出版社、1987年、181頁‐191頁。
- 小松弘「澤田正二郎と映画」、児玉竜一【監】/羽鳥隆英【編】『寄らば斬るぞ!新国劇と剣劇の世界』、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、2014年、30頁‐36頁。
- 「人物リサーチ――この個性豊かな男たち」3、『平凡スタア』第2巻第7号、平凡出版、1976年、77頁。
- 「笠原章、新国劇を語る」、註⑶、児玉【監】/羽鳥【編】、127頁。
- 児玉竜一「天皇を演じる歌舞伎役者」、岩本憲児【編】『映画のなかの天皇――禁断の肖像』、森話社、2007年、211頁。
本論はJSPS科研費JP22K00128の助成を受けた研究の一環である。